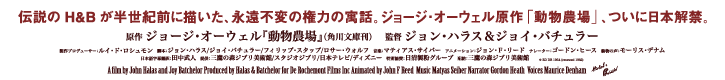Main Contents

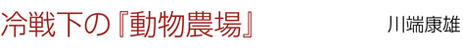
イギリスのアニメーション・スタジオ、ハラス&バチュラーによる「動物農場」が完成したのは一九五四年秋で、ニューヨークでのワールドプレミアでお披露目されたのは同年暮れのことだった(英米での一般公開は一九五五年一月)。イギリス初の長編カラー・アニメーション映画として特筆されるこの作品については、近年、新史料の発掘などもあって、文化史やメディア研究などの分野からその制作の経緯について新たな光が与えられている。本稿は、それらの新たな知見をふまえつつ、原作者ジョージ・オーウェルの創作意図、また受容のされ方を併せて見ながら、映画化の経緯、原作との異同、またその意味合いについて、紙数の許す限りでスケッチを試みてみたい。
原作の『動物農場』の初版刊行の日付は一九四五年八月十七日である。日本がポツダム宣言を受諾して降伏したのが八月十五日、これで第二次世界大戦が終結したわけなので、まさに終戦時に(そして広島、長崎の原爆投下と同月に)これが出たことになる。これをオーウェルは戦争中に書き、一九四四年二月には完成させている。脱稿後ロンドンの四つの出版社にもちかけたのだが、四四年七月までにすべて断られた。理由はこれがソ連批判の書であったためである。同年八月末にセッカー・アンド・ウォーバーグ社が引き受けることに決まったが、戦時中の紙不足のためにさらに延び、一年後にようやく刊行の運びとなった。書店に並ぶやいなやこれが大ヒット、翌四六年には米国でも刊行され、たちまちベストセラーとなる。さらにそのあと、各国語版の翻訳刊行がつづく。大ヒットの理由は、ソ連批判の書であったからだ。
ソ連批判の書であるがために刊行が難航し、刊行されるとおなじ理由でベストセラーになったというのは、矛盾した話に聞こえるが、英米とソ連の関係が終戦時を境目として大きく様変わりした事実を示せば、納得していただけるであろう。ソ連とドイツとは大戦が勃発した時点では独ソ不可侵条約を結んでいたが、一九四一年六月にドイツがソ連侵攻を開始するとソ連はイギリスと同盟を結び、ドイツを共通の敵として戦うことになった。米国もソ連への援助を開始した。四三年二月のスターリングラード攻防戦でのソ連の勝利が大戦全体の画期となったのだが、オーウェルが出版社を模索していた一九四四年においても、連合国側のソ連の役割は重要だった。『動物農場』の企画を断った三つの出版社は、そのような戦時の国際関係と国民感情を配慮して、その原稿を却下したのである。
ところが戦後、米ソ二大国を中心としたブロック化が急速に進み、両陣営の対立構造が強まる。一九九一年のソ連解体までつづく冷戦体制の到来である。ソ連の東側ブロックには東欧諸国などが共産圏として、米国を中心とする西側ブロックには西欧諸国や日本をふくむ世界各地の資本主義国が組み込まれ、双方を仮想敵とみなして、険悪な敵対関係が生じた。そのような戦後体制にむかおうとする転機にこの物語が出たというのは、話題性という点からすると、まことにタイムリーだったのである。
「ソビエト神話の正体をあばく」
動物寓話のかたちをとる『動物農場』には実名はひとつも出てこないが、ロシア革命以後のソ連史をふまえているのは一目瞭然だった。オーウェル自身、この物語を書いた動機は、「だれにでも容易に理解でき、他国語にも容易に翻訳できるような物語によって、ソビエト神話の正体をあばく」ことだったと述べている。「ソビエト神話」とは、平たく言えば、「ソ連(ソビエト社会主義共和国連邦)の政治体制について人びとがいだいていた、まちがった思い込み」ということであり、ソ連を階級差別と貧富の差が消えた輝かしい理想の共産主義国とみなす(彼にいわせれば当時の左翼知識人が抱きがちな)幻想を指すものだった。神話化(理想化)のあまり、その暗黒面が見えなかった。その最たるものが「粛清裁判」だった。
一九一七年の三月革命でロマノフ王朝が倒され、十月革命でボルシェビキ(共産党多数派)によりソ連が樹立、その指導者であったレーニンの時代でもすでに共産党の一党独裁が進められていたが、レーニンが表舞台から消えた頃から、スターリン独裁体制の地固めとして、テロとしての「粛清」がじわじわと進んでゆく。レーニン没後の一九二五年には最大の政敵トロツキーを失脚させる。性格的にも対照的なスターリンとトロツキーの役割は、『動物農場』ではそれぞれナポレオンとスノーボールという二頭の豚が演じている。結局トロツキーは党から除名され、国外追放の処分を受ける(最後は一九四〇年にメキシコで暗殺)。物語ではナポレオンが子飼いの猟犬をけしかけてスノーボールを農場から追放するくだりでそれが描かれる。
こうしてスターリンは、ほかにも多くの政敵を排除してゆき、やがて一九三六年の第一次モスクワ裁判に至る。スターリンのかつての同志ジノビエフらが逮捕され、でっち上げられた罪状を認め、裁判がすむとすぐに銃殺刑に処された。これを初めとして、身に覚えのない罪で告発され、ありもしない自白を強要されるという、国家裁判が無数になされる。「人民の敵」を追及する「粛清」という名のテロルは一九三八年までつづき、その数年間に、共産党幹部から農民に至るまで、数百万人が犠牲になったとされる。
この粛清裁判は『動物農場』では、ナポレオンに反抗した豚や鶏が中庭に引き立てられて、スノーボールの手先であったと自白させられる場面で描かれる。自白を終えた彼らは犬に食い殺される。「この動物たちはみんなその場で殺されました。こんなふうにして、告白と処刑はえんえんとつづき、しまいにはナポレオンの足下に死がいの山ができてしまい、血なまぐさい空気がたちこめました。」
このように、ソ連史の重要な局面が『動物農場』のなかに書き込まれている。ロシア革命はもとより、一九二五年以後の第一次五ヶ年計画などの農業集団化計画の破綻(風車建設のエピソード)、三九年の独ソ不可侵条約の締結、その条約を破っての四一年のドイツ軍によるロシア侵攻、そして四三年のテヘラン会談に至るまでの経緯が動物寓話のかたちをとってきっちりと書き込まれている。
そのようなソ連の実態をオーウェルが認識したのはスペイン内戦に参加した経験によるものだった。一九三六年の暮れにバルセロナ入りした彼は、翌三七年初めに民兵組織ポウム(マルクス主義統一労働者党)に入隊。アラゴン戦線の塹壕で冬をすごし、春に一時休暇をえてバルセロナに滞在していたときに、共和国政府側のセクト争いによる市街戦を目撃する。その後アラゴン戦線にもどったが、敵の狙撃で銃弾が首を貫く重傷を受け入院。さらにはポウムに対する共産党の粛清がはじまり、彼の身もあやうくなったが、危機一髪のところでフランスに脱出。これについては、ルポルタージュ文学の傑作である彼の『カタロニア讃歌』(一九三八年)に詳しい。
オーウェルがスペイン内戦に関わったとき、まさにソ連本国は粛清の真っ只中で、その余波をこうむったということになる。ファシズムに対して共に戦っているはずが、自分の所属した民兵部隊が「トロツキー主義者」の名で共産党から迫害され、仲間の多くが投獄されたり殺されたりし、彼自身の命もおびやかされた。その恐怖を身をもって体験したことが、いち早く「粛清」という聞こえのよい名のテロ行為の暴虐さを認識し、ソ連を理想国家と見る「神話」をあばかなければならないと確信させたのだった。そしてこうした批判をオーウェルはあくまで自身の信奉する「民主的社会主義」としての立場からおこなっていたのである。
「反共作家」の効用
『動物農場』につづき、一九四九年に『一九八四年』を刊行したオーウェルは、翌五〇年一月に四十六歳の若さで病没する。冷戦構造が固まってゆく世界情勢のなかで、西側陣営の先鋒に立つ者、特に米政府筋は、反ソ=反共主義を体現するアイコンとしてオーウェルを活用してゆく。その際に、彼自身の社会主義者としての信条は隠して、ソ連の体制のみならず、冷戦体制の西側(資本主義)陣営の正統的教義にとって望ましからぬ共産主義および社会主義思想全般に敵対する存在としてオーウェルを祭りあげる傾向が、特に米国を中心にして強まる。そのように使われては困るという趣旨の発言を彼は生前にしているが、それは聞き届けられなかった。
米国政府はオーウェルの本を三十ヶ国語以上の言語に翻訳・配布するための資金援助をおこなった。一九五一年の「国務省の反共闘争における書物の関与」と題する回状(内部資料)では、『動物農場』と『一九八四年』は「共産主義への心理戦という面で国務省にとって大きな価値を有してきた」と指摘し、「その心理的な価値ゆえに、国務省は公然と、あるいは内密に、翻訳の資金援助をすることが正当であると感じてきた」と記されている。日本での『動物農場』と『一九八四年』の最初の翻訳刊行もまさしくこのような流れのなかで米国の主導によって推進された。GHQ(連合軍総司令部。実質上は米軍が仕切っていた)の統制下で敗戦後の日本は外国文献の新規翻訳が凍結されていたのだったが、一九四九年にGHQの認可を受けた「第一回翻訳許可書」として『アニマルファーム』(永島啓輔訳、大阪教育図書)が刊行された。『一九八四年』も原作刊行の翌年の一九五〇年に邦訳が出ている。
アニメーション化の経緯
『動物農場』の映画化の企画が具体化するのはオーウェルが没してから後のことだった。映画化の版権を許可したのは、相続人としてその著作権を受け継いだ妻のソーニア・オーウェルだった。前妻アイリーンとは一九四五年に死別しており、文芸誌『ホライズン』の編集秘書を務めていた十五歳年少のソーニアと再婚したのは、オーウェルが肺結核で死去する三ヶ月前のことだった。
ハラス&バチュラーのアニメーション「動物農場」の制作資金をCIA(米中央情報局、一九四七年に創設)が出しているのではないかという噂は、公開当時からすでに一部で囁かれていたことだが、それを部内者が最初に公表したのは、CIAの諜報員であったハワード・ハントによってである。一九七二年のウォーターゲート事件に連座して悪名をはせたハントは、七四年に出した回想記で自身がアニメーション制作に深く関与したと示唆しているが、それは怪しい。ソーニアから映画化権を得るのに彼女が好きなハリウッド俳優クラーク・ゲイブルに会わせるという約束で釣ったというエピソードをはじめ、従来流布してきた説には眉唾物めいたところも多く含まれる。しかしCIAの資金援助が事実であったことは、製作者ルイ・ド・ロシュモンの関連文書を発掘して証拠資料として用いたダニエル・リーブの近著『覆されたオーウェル─CIAと「動物農場」の映画化』(ペンシルバニア大学出版局、二〇〇七年)で論証されている(以下の記述はこれに拠るところが大きい)。近年の調査研究によって、CIAの出資は、もはや噂ではなく、事実であると確証されている。
CIAは、冷戦体制化における心理戦の一作戦として、OPC(政策調整局、心理戦のために一九四八年に設置、五一年にCIAに統合)と連携して『動物農場』の映画化を企画し、ド・ロシュモンを抜擢して、制作資金を秘密裏に供給した。五一年にド・ロシュモンは、その制作会社としてハラス&バチュラーを選定。契約書を同年十月末に交わした。この会社はハンガリー出身のアニメーターのジョン・ハラスが同業者のジョイ・バチュラーと共同で一九四〇年にロンドンで立ち上げたもので(同年に二人は結婚)、英政府依頼の作品や企業のPRアニメーションなどで実績をあげていた。米国の会社に比べて制作費を安く抑えられるというのもイギリスの制作会社に依頼した要因のひとつだった。制作期間と費用は当初の予定を大幅に超え、五一年の秋から三年かけ、当初二十人の小規模で始めたのが一年のうちに七十人を超える大所帯の制作チームとなった。
この「作戦」が「秘密工作」であった以上、著作権者のソーニア・オーウェルに対してはもとより、ハラスとバチュラーにもCIA関与の実態が伏せられていたのは当然であり、表向きはド・ロシュモンの映画制作会社RD─DR(Reader’s Digest - de Rochemontの頭文字を取ったもの)が制作に従事するということで進められたが、ハラス&バチュラーには「投資者(investors)の意向」という説明でぼかしつつも、当初から脚本およびキャラクターの描き方について具体的で細かい「要望」がなされた。コンピュータ導入のはるか以前、デジタル彩色などありえず、すべてを手作業でおこなうしかなかったこの時期に、十八のシークエンス、七百五十のシーン、カラー原画三十万枚を描くのに膨大な労力と時間がかかったということがもちろんあるが、遅延のもうひとつの理由としては、プロット等の変更の「要望」(事実上の「強要」)を受けてジョイ・バチュラーが脚本(九稿におよんだ)やストーリーボードを何度も描き直すなど、度重なる変更を強いられたこともある。その変更に伴って多量の原画がボツになった。
「投資者」たちの「要望」
そのような事情で、オーウェルの物語を原作としつつも、ハラス&バチュラーのアニメーション版はいくつかの重要な相違点が生じた。その最たるものが、結末の変更である。ナポレオンの独裁体制が固まって、「すべての動物は平等である」という本来のスローガンに「しかし一部の動物はほかの動物よりももっと平等である」が加わるというのは後者でも踏襲している。だが、原作で、ナポレオンが敵であったはずの人間たちを農場に招待して、和気あいあいと宴会に興じていたところ、トランプゲームのペテン騒ぎで双方のいがみあいになり(結びの段落を拙訳で掲げると)、
十二の声が怒って叫んでいました。そしてその声はみんなおんなじようでした。いまや、ぶたたちの顔がどうなってしまったのか、うたがいようはありませんでした。外から見ていた動物たちは、ぶたから人間へ、人間からぶたへ、そしてぶたから人間へと目をうつしました。でも、もう無理です。どっちがどっちだか、見わけがつかなくなっていたのです。
とあるのが、アニメーション版では、人間は登場せず、堕落した豚たちについに堪忍袋の緒が切れた他の動物たちが(原作では最後まで「非政治的」な「静観主義者」だったロバのベンジャミンが、ここでは親友の馬ボクサーが豚の陰謀によって悲惨な最期を遂げたのを契機についに目覚め、リーダーとなって)外部の動物たちの援軍を得て反乱を起こし、豚を退治するというハッピーエンドになる。
映画史家のトニー・ショーによれば、バチュラーは「原作の結末どおりにしたい」と願っていて、「部外者の干渉にしだいに不満を覚えるようになっていた」というが(『英国映画と冷戦』二〇〇一年)、結末の変更は制作の初期段階から既定路線となっており、あくまで原作どおりの結末で、という強い姿勢は取っていない。ハラスについていえば、ニューヨークでのプレミア上映の直後に一人の女性が感涙にむせんで彼に抱きついてきたので、「ただのアニメの物語なのですから」と言って相手を落ち着かせたというエピソードがある(G・ベンダッツィ『カートゥーン─アニメーション映画百年史』による)。結末をそのように変えたからこそ、感銘を与えられたのだとハラスは示唆している。
一九一二年にハンガリーのブダペストで生を享けたジョン・ハラスは、下積み生活ののちにブダペストで仲間とアニメーション・スタジオを設立、その仕事が注目されて三六年にイギリスのスタジオから声がかかって渡英(バチュラーとの縁がここでできる)。ハンガリーは第二次世界大戦ではドイツの圧力で枢軸国への加担を余儀なくされ(ユダヤ系のハラスはこれで事実上の亡命者となる)、戦後はソ連の衛星国として共産主義体制下に置かれる。「動物農場」の制作期間はラーコシの恐怖独裁政治の時期にあたり、ハラスが母国の身内や友の境遇を案じつつ制作にあたっていたことは想像に難くない。その点で、「投資者」の思惑とは別に、豚を打倒する結末にする個人的な動機は十分にあったわけだ。完成の二年後の一九五六年、ハンガリーでは独裁政権に対する大規模な民衆蜂起が起こる。だがこれは、アニメーションの大団円とは異なり、ソ連が介入して徹底的に弾圧、蜂起した民衆のうち数千人が死亡し、およそ二十万人が亡命する。
しかし「投資者」にとってはこうした変更は心理戦の効果を狙った政治的な配慮以外のなにものでもなかった。上記の結末の改変は、共産圏に対する米国政府の「封じ込め」作戦から「巻き返し」作戦への政策転換を反映している。一九五三年にダレス国務長官はこの「巻き返し」政策を声高に唱えた。共産圏で「奴隷」とされた諸国民を看過せず、積極的な行動によって解放してやらなければならない、という考えである。結末をこの作戦にダブらせることが「投資者」にとっては肝心なことだった。そのためには結末で人間(資本主義者)を豚と同列にしてしまうのは具合が悪い。ピルキントンやフレデリックは必要ない。農場の奪回作戦に関わるのも農場主たちではなく、ジョーンズとその手下だけでよい。「悪い農場主は一人しかいない」のだから。スノーボールの同情的な描き方はいかがなものか。スノーボール(トロツキー)が追放されずにいたら動物農場(ソ連)はまともな社会になっていただろうと受け取られてしまう。政権に就いてもなにもできない無能で狂信的なインテリとして描くべし。外部の動物たちの描き方も要注意。善人が経営する農場(西側陣営)では動物は自由で満ち足りて幸福なのだからそのように描くべし─等々、「投資者」たちは、最初から最後までこのような修正意見を出しつづけた。彼らの見解では、バチュラーの初期の脚本には「共産主義そのものは正しいのにスターリン一味のせいでそれが裏切られたのだとする思い込み」が見られるが、これは資本主義社会についての彼女の「消極的な描写」とともに、「われわれには受け容れがたい」として、そうした「誤解」がなくなるまで、脚本の書き直しが求められた。
「ニュースピーク」のアニメーションは可能か?
「投資者」たちの異常に細かい修正意見をながめてみて連想させられるのは、皮肉なことに、『動物農場』原作の結びの「どっちがどっちだか、見わけがつかなくなっていた」という一文である。アニメーターを管理・操作しようとしつづける「投資者」グループは、体制の維持のために人間の意識をいかに狭めるかに腐心している点で、彼らが叩くことを公言している全体主義的なメンタリティを事実上反復している。
オーウェルのもうひとつの問題作『一九八四年』でいうならば、彼らは「ニュースピーク(newspeak)」の原理にしたがって『動物農場』の改変をめざしていたといえるだろう。その原理は、現実世界の認識方法を支配するべく、使用語彙の削減や統語法の組織的な操作によって、思考の範囲を縮小することをめざす。これによって「正統思想」以外は発想しえなくなる。「ニュースピーク」が示す「現実」とは、つねにその支配体制の永続化に資するものでなければならない。そのために、あらゆる手段をつくして言語を権威的に支配し、異端思想につながる変化を阻止する。ひとつの語はひとつの正統的な概念のみを厳密に指示すべきであって、それ以外は除去されるべきである。「意味されるもの」と「意味するもの」の厳密な対応。「ナポレオンはスターリンであり、スノーボールはトロツキー」なのだから、ナポレオンにはパイプをくわえさせ、「スターリンの口髭を示すようにカールさせた剛毛」をつけ、スノーボールは「トロツキーの山羊ひげを示すようなひげをつける」ようにしたらいかがか、そう「投資者」たちは注文をつける。
しかしながら、言語の本性上、そしてアニメーションという視(聴)覚メディアの本性からいっても、それは無理なのである。「アレゴリー」という、比喩の有機的な連なりを命とする形式を用いた物語を機械的に「ニュースピーク」流に翻訳しようとすることの背理に「投資者」たちはあまりにも無自覚で、寓意の「主意」とそれが仮託された「媒体」とを逐語的に一対一対応の解釈しかできないように仕組んで、しかもそれが成功しうる、という単純素朴な言語観に私は思わず笑ってしまったのだが、冷戦下の心理戦で両ブロックがなにをしたかを考えてみれば、もちろんこれは笑いごとではすまされない。
「投資者」たちの誤算
オーウェルの原作は、「ソビエト神話」の暴露という当初の意図を超えて、その寓話の語りの力によって、冷戦終結以後、ソ連が消えたあとも、あらゆる政治権力の腐敗を風刺した普遍的な書物になっていると私は考える。ではアニメーション版は? CIAのエージェントたちの狙いは首尾よく果たされたのであろうか? 「ニュースピーク」的な、意識の狭まりを強要する「投資者」の意図が徹底し、それが成功していたとしたら、プロパガンダ映画の最低の部類として、もはやそれが顧みられることはなかったであろう。しかしながら、出来上がった作品は彼らの思惑どおりの効果はおよぼさなかった。当時の映画評にそれはうかがえる。解釈が一様ではないのだ。米国の親ソの左翼誌『ネイション』がこれをひどい反共宣伝とみなしてオーウェル攻撃を再開したのは予想されたことだが、保守層あるいは反共の批評家たちは必ずしもこれを歓迎しなかった。監督に「トロツキー主義」への共感の念があるのではないかと懸念した評者がいた。米国の別の評者は、ハラス&バチュラーが戦時中に英政府のために反ナチ宣伝映画を多く手がけたことにふれて、彼らがオーウェルのメッセージを「左翼的」にねじまげて、風刺の矛先をロシア革命から別のものに故意にそらしたのではないかと疑った。
時あたかも、米国内では一九四八年頃からマッカーシズムの嵐が吹き荒れ、政界、映画界などで「共産分子」を糾弾・追放する「赤狩り」が進行していた。そのなかで偽証、事実の歪曲、自白の強要、友の裏切り、密告の奨励がなされ、人心は荒廃した。こうした「粛清」の行き過ぎにようやく歯止めをかけるかたちで、米上院がマッカーシー議員の非難決議をおこなったのは、「動物農場」のプレミア上映とおなじ一九五四年十二月のことだった。一種の国民的なヒステリー状態から醒めつつあったときであり、米国の観客にすれば、映画を観て、遠くモスクワを思い浮かべずとも、もっと身近なところに、思い当たることがあった。
「投資者」たちに投資のし甲斐があったのかどうか─当てが外れたのだと思う。ハラスたちを操作して、狙いどおりのアニメーションを作らせる、というもくろみは崩れた。CIAは一九五三年にイラン政府、五四年にグアテマラ政府の転覆作戦を仕掛けて成功し、両国はとんでもなく悲惨な状況に陥ったが、アニメーション作戦については思惑がはずれた。なるほど、私見では、彼らの「要望」を容れたために、原作のインパクトが映画版で削がれてしまった部分はたしかにある。「投資者」たちの愚かな介入がなかったらよかったのに、と残念に思うところもある。しかしながら、いま紹介した公開当時のさまざまな評にうかがえるように、映画を観た人びとは自分の生きる場のそれぞれの現実にこの物語を置き換えて、その寓意を解釈しようとしたのである。寓話というものが本来そうであるように、現実世界を把握し、その意味を探るための思考の道具として、それは機能した。「投資者」には予想外なことに、彼ら自身も風刺の対象に含まれることになった。風刺の精神はアニメーションのなかにしぶとく生きのこっていたのである。
ハラス&バチュラーの、特殊な圧力と障壁を乗り越えるねばり強さ、反骨精神、志の高さと熱い想いがあってのことだろうが、それはまたアニメーションそのものが秘める積極的な可能性を示すものでもあるのだろう。ジョイ・バチュラーが後年アニメーション史家のベンダッツィに語ったところによると、「動物農場」の制作に際して彼女とジョン・ハラスがめざしたのは、「自由についての映画」をこしらえることなのだった。
川端 康雄
一九五五年、神奈川県生まれ。
日本女子大学文学部教授。英文学、イギリス文化研究。明治大学大学院文学研究科博士課程後期退学。著書に『オーウェルのマザー・グース』(平凡社)、『「動物農場」言葉・政治・歌』(みすず書房)、『絵本が語りかけるもの』(共著、柏書房)、訳書に『オーウェル評論集』(編・共訳、平凡社)、ウィリアム・モリス『世界のはての泉』(共訳)、『ユートピアだより』(ともに晶文社)、『理想の書物』(筑摩書房)などがある。