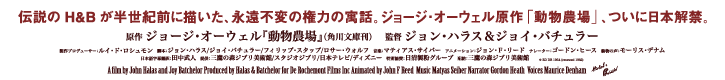Main Contents

「投資者」たちの誤算
オーウェルの原作は、「ソビエト神話」の暴露という当初の意図を超えて、その寓話の語りの力によって、冷戦終結以後、ソ連が消えたあとも、あらゆる政治権力の腐敗を風刺した普遍的な書物になっていると私は考える。ではアニメーション版は? CIAのエージェントたちの狙いは首尾よく果たされたのであろうか? 「ニュースピーク」的な、意識の狭まりを強要する「投資者」の意図が徹底し、それが成功していたとしたら、プロパガンダ映画の最低の部類として、もはやそれが顧みられることはなかったであろう。しかしながら、出来上がった作品は彼らの思惑どおりの効果はおよぼさなかった。当時の映画評にそれはうかがえる。解釈が一様ではないのだ。米国の親ソの左翼誌『ネイション』がこれをひどい反共宣伝とみなしてオーウェル攻撃を再開したのは予想されたことだが、保守層あるいは反共の批評家たちは必ずしもこれを歓迎しなかった。監督に「トロツキー主義」への共感の念があるのではないかと懸念した評者がいた。米国の別の評者は、ハラス&バチュラーが戦時中に英政府のために反ナチ宣伝映画を多く手がけたことにふれて、彼らがオーウェルのメッセージを「左翼的」にねじまげて、風刺の矛先をロシア革命から別のものに故意にそらしたのではないかと疑った。
時あたかも、米国内では一九四八年頃からマッカーシズムの嵐が吹き荒れ、政界、映画界などで「共産分子」を糾弾・追放する「赤狩り」が進行していた。そのなかで偽証、事実の歪曲、自白の強要、友の裏切り、密告の奨励がなされ、人心は荒廃した。こうした「粛清」の行き過ぎにようやく歯止めをかけるかたちで、米上院がマッカーシー議員の非難決議をおこなったのは、「動物農場」のプレミア上映とおなじ一九五四年十二月のことだった。一種の国民的なヒステリー状態から醒めつつあったときであり、米国の観客にすれば、映画を観て、遠くモスクワを思い浮かべずとも、もっと身近なところに、思い当たることがあった。
「投資者」たちに投資のし甲斐があったのかどうか─当てが外れたのだと思う。ハラスたちを操作して、狙いどおりのアニメーションを作らせる、というもくろみは崩れた。CIAは一九五三年にイラン政府、五四年にグアテマラ政府の転覆作戦を仕掛けて成功し、両国はとんでもなく悲惨な状況に陥ったが、アニメーション作戦については思惑がはずれた。なるほど、私見では、彼らの「要望」を容れたために、原作のインパクトが映画版で削がれてしまった部分はたしかにある。「投資者」たちの愚かな介入がなかったらよかったのに、と残念に思うところもある。しかしながら、いま紹介した公開当時のさまざまな評にうかがえるように、映画を観た人びとは自分の生きる場のそれぞれの現実にこの物語を置き換えて、その寓意を解釈しようとしたのである。寓話というものが本来そうであるように、現実世界を把握し、その意味を探るための思考の道具として、それは機能した。「投資者」には予想外なことに、彼ら自身も風刺の対象に含まれることになった。風刺の精神はアニメーションのなかにしぶとく生きのこっていたのである。
ハラス&バチュラーの、特殊な圧力と障壁を乗り越えるねばり強さ、反骨精神、志の高さと熱い想いがあってのことだろうが、それはまたアニメーションそのものが秘める積極的な可能性を示すものでもあるのだろう。ジョイ・バチュラーが後年アニメーション史家のベンダッツィに語ったところによると、「動物農場」の制作に際して彼女とジョン・ハラスがめざしたのは、「自由についての映画」をこしらえることなのだった。
川端 康雄
一九五五年、神奈川県生まれ。
日本女子大学文学部教授。英文学、イギリス文化研究。明治大学大学院文学研究科博士課程後期退学。著書に『オーウェルのマザー・グース』(平凡社)、『「動物農場」言葉・政治・歌』(みすず書房)、『絵本が語りかけるもの』(共著、柏書房)、訳書に『オーウェル評論集』(編・共訳、平凡社)、ウィリアム・モリス『世界のはての泉』(共訳)、『ユートピアだより』(ともに晶文社)、『理想の書物』(筑摩書房)などがある。