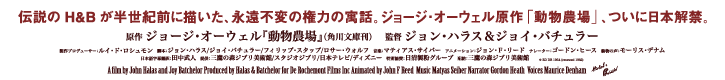Main Contents

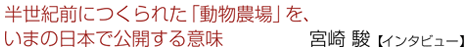
―「動物農場」との出会いから聞かせてください。
ハラス&バチュラーの「動物農場」が、ぼくの記憶にとどまっていたのは、ジョン・ハラスがつくったアニメーション技術の本があるんです(『アニメーション─理論・実際・応用─』ジョン・ハラス、ロジャー・マンベル著、伊藤逸平訳、東京中日新聞出版局、一九六三年)。ぼくがアニメーションの仕事をはじめたのは一九六三年ですが、そのころアニメーションの技法書といったら、このジョン・ハラスの本と、あとはロシアの本くらいしかなかったんです。ロシアの本はあまり役に立つことはなくて、ただ一点だけ、「言語的に面白いものが、映像的に面白いとは限らない」という教訓が書いてあって、それだけは印象に残ってるんですが。
ジョン・ハラスの本は、撮影上のことやら作画上のことやら、いろんなことを含めて自分たちの経験を盛り込んだ、ぶ厚い本でした。そのなかに「長編アニメーション」という項目があって、「長編アニメーションをつくる者たちは、いままで誰も耕したことのない石ころだらけの荒地に鍬を打ち込むような思いを味わうだろう」というようなことが書いてあったんですよ。「動物農場」をつくった後にこの本を書いていますから、彼ら自身がそんな思いを味わったということですよね。「動物農場」は、商業的にはみごとに失敗したんです。
長編アニメーションというのは、第二次世界大戦が終わって、五〇年代に入る頃にあちこちでつくられるようになります。フランスでは「やぶにらみの暴君」(ポール・グリモー監督、一九五三年。一九八〇年には作者完成版「王と鳥」として公開)、ロシアでは「せむしのこうま」(イワン・イワノフ=ワノ監督、一九四七年。のちに「イワンと仔馬」に改題)や「雪の女王」(レフ・アタマーノフ監督、一九五七年)という傑作がつくられ、そしてイギリスでつくられたのが「動物農場」だったわけです。もちろんアメリカではウォルト・ディズニーがすでにたくさんの長編アニメーションをつくっていましたが、技術的にあまりにも自分たちとかけはなれているので、どう学んでいいのかわからない(笑)。それとくらべると、「やぶにらみの暴君」や「雪の女王」のほうが、技術的にも心情やテーマの部分でも、自分たちに引き寄せやすかったんですね。ですから、ぼくらの世代にとっては、長編アニメーションをつくりたいと思ったときに、お手本としていくつかあるなかの一本だったんです。
だけど、ジョン・ハラスの本を読んでから実際に「動物農場」を見るまでには、もう少し時間がかかりました。たまたまテレビでやっているのを見たんですけど、「よくこんなものをつくったな」と思いました。子供たちが見ることを前提につくったものではないんです。
―当時としては珍しい、大人向けの長編アニメーションですね。
当時のイギリスは、第二次世界大戦が終わり、冷戦が始まろうとしているときです。第三次世界大戦が始まるんじゃないか、原爆の戦争が始まるんじゃないかという恐怖、と同時に、恐ろしい勢いでふくらもうとするソ連があって、世界中がソ連型の共産主義になったら大変だ、という危機感が強かった。
ジョージ・オーウェルはまさにそれを考えて、『動物農場』や『一九八四年』という作品を書いたんですよね。それは、ハラス&バチュラーも同じ気持ちだったと思います。ハラスはハンガリー出身のユダヤ人ですから、推測するに、ハンガリーからイギリスへ亡命した人でしょう。自分たちの祖国は、戦時中はナチスドイツの、戦後はソ連の支配下にあった。まさに『動物農場』で描かれているような、独裁者が君臨している全体主義的な世界にリアリティがあったんです。彼自身にとって、ものすごく今日性のあるテーマだった。だからこそ、この映画をつくろうと思ったと思うんです。口ではうまいことを言いながら、まじめな人間たちをこき使って、自分は権力の上にあぐらをかいている、そういう人間の醜さをえぐり出したいと思ったんでしょう。
だけど、搾取とか収奪というのは、なにも共産主義だけにあるんじゃなくて、資本主義はまさにそういう「しくみ」です。ぼくは会社というのは、誰よりもそこで生活しながら仕事している人間たちの共有の財産だと思っています。でも、それは社会主義的な考え方なんですね。いま、主流になっている考え方というのは、私有財産として株をもっている人間のほうに発言権があって、株主たちが「この経営者はダメだ。もっと儲ける経営者を選べ」といったら、経営者はどんどん変わらなきゃいけないとか、そういうアメリカ型の資本主義です。それを進めていくと、リストラをして正社員を減らして、派遣社員やアルバイトだらけにして、労働基準法のギリギリまでこき使ってポイッと捨てる。正社員は正社員でくたくたになって働いてる。いくらでも替わりはいるんだという、いまのしくみこそ、「動物農場」と同じです。
これがこの世のなかのしくみだというのは、ある時代までは常識だったんです。だけど、いつのまにか、みんなそれを忘れてしまってたんです。みんなが中産階級だと思いこむことによって、搾取の構造というのは見えなくなっていた。と同時に、戦後の日本の経済成長のなかでは、経営者も必死に働かないといけなかったし、日本は累進課税で、トップと末端の所得格差が少ない国だったんですよ。バブルの前までは、そういう社会が一時あったんです。だから支配や搾取の構造には、リアリティが薄くなっていたんですよ。少しは平等感のある社会になってきたと思ったら、バブルで足をすくわれて全部崩れた。終身雇用制もあっというまに捨てたし、年功序列も捨てた。そして能率給だとか、目標設定するとかってやりはじめた。能率給なんかにしたら、神経症になるだけだと思いますけどね。ふつう才能があるのなら、損得はあとまわしで力をつくして仕事をするのは当然で、金のために仕事するなって。いや、金のために働かなきゃいけないんだけど、そういう考え方は自分を貶めることになりますから。まあ、いろんな考えがありますが、ぼくたちは「仕事は人生の伴侶だ」ということでやるものと思い、そうしてきました。