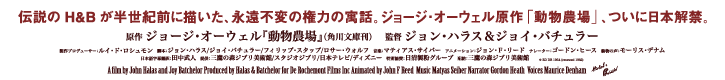Main Contents

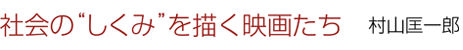
近頃、売れ行きが伸びて話題になっている小説に『蟹工船』がある。小林多喜二が1929年に書いたプロレタリア文学の代表作のひとつ。年号でいえば昭和4年、いまからおよそ80年前の小説になる。小林多喜二が1933年に官憲の拷問によって殺されたことは知られるが、彼の『蟹工船』は、昭和はじめの不況と軍国主義の台頭による反対派の抑圧という時代背景のなかで書かれたものである。その小説がなぜいま読まれているのか。
『蟹工船』の読者の多くは、ワーキングプアとよばれる人々といわれる。ワーキングプアとは、いわゆるフリーターなど、就労しているにもかかわらず貧困生活を送らざるをえない人々のことをいうが、平成不況による「待ち組」とよばれる若い人々もふくめて、その数は年々増えているらしい。こうした貧富の格差を生み出す大きな原因は、資本主義という経済システムにある。そして、この80年のあいだには、戦争や政治制度の転換や物質的な繁栄といった、いろいろな変化があったにしても、そのシステムは本質的に何も変わってはいない。ただ今日のように個人の「自由」が謳歌される社会では、根本的な原因について語るよりも、「自己責任」という曖昧な言葉で貧富の格差をかたづける傾向が強くなっている。
ところで、この『蟹工船』は、小説の発表から四半世紀を経た1953年に映画化されている。俳優の山村聡が監督・脚本・主演を兼ねて独立プロで製作したものである。当時は、第2次大戦後の民主主義の顕揚のなか、「来なかったのは軍艦だけ」といわれた東宝争議に象徴される左右のイデオロギーの対立が激しく、多くの左翼的な映画人が独立プロに依拠して映画製作をおこなっていた。そんな時代のなかで『蟹工船』は映画化されたわけである。ただこの小説は、昭和はじめの時代を背景にしながらも、資本主義という社会の“しくみ”をあらわにするという意味で普遍的な性格を持っており、だからこそ映画化からさらに半世紀以上を経た今日でも読み継がれているといえる。