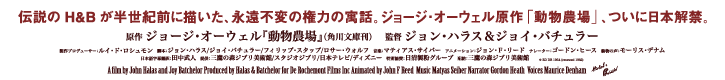Main Contents

「動物農場」こそ、すべての独裁国家に
必要と思った一九九四年の頃。
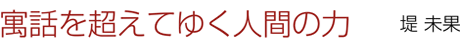
一九九四年の秋。ニューヨーク郊外にある大学寮のひと部屋に政治学専攻の学生数人が集まった。レポート課題で出されていたアニメーションのビデオを観るためだ。タイトルは「動物農場」。一九四五年にジョージ・オーウェルという作家が、ロシア革命および共産革命下の旧ソ連をモデルに描いた寓話だ。舞台は農場。そこにいる動物達は働けど働けど悲惨な生活を送っている。オーナーである人間が動物達の労働をすいあげて消費するだけの不公平な構図に、ある時一匹の老豚が声をあげ動物たちに革命を起こせと呼びかける。奮起した動物たちは二匹の豚をリーダーにみごと革命を成功させ人間を農場から追い出した。彼らは貧しさとは無縁の、全ての動物が平等である社会がやってくるという夢とともに意気揚々と農場経営を始める。だが数カ月もたたないうちに権力におぼれた豚たちの独裁政治が農場全体をのみこんでゆき、動物たちは再び搾取の構造の下層部へと転落してゆく。
何て面白い作品だろう。私はオーウェルの人間観察力に感動し、興奮してその場にいた他の学生達にそう伝えた。ビデオを持ってきたマシューというアメリカ人はこれは日本の「AKIRA」と並び自分の気に入りの作品だと誇らしげに語った。出てくるキャラクターに作者が現実の誰をあてはめて描いたのか、解説を始めたのはミンキョンという韓国人だ。レーニンにスターリン、トロツキー……、教科書で読んだ歴史上の人物と動物たちの特徴がいかに絶妙に重なりあっているか。どんなに頭の中で理想を描いても、現実に反映させた途端いとも簡単にファシズムに転化していく共産主義のもろさについて。チェンとナターシャという二人の学生は黙って部屋を出ていった。「仕方ないわよね」とミンキョンが肩をすくめた。チェンは中国から、ナターシャはロシアからの留学生だったからだ。「こういう作品はああいった国でこそ観られるべきだがなあ」。マシューの言葉に、あの時私はこう思ったのを覚えている。「権力欲におぼれ道を誤る」という、オーウェルが描いた人間の性。出口のないその現実を忠実に寓話に反映させた「動物農場」こそ、今世界中で同じ過ちを犯しているすべての独裁国家に必要なものなのではないかと。マシューの勧めで「動物農場」を再び最初から見たあとで、私はレポートにそう書いた。
今ならわかる。あの頃の私にとって何故この作品があんなにも魅力的だったのか。一部の人間に支配され奴隷のように搾取される社会構造が、所詮他人事だったからだ。
右肩上がりのバブル期に留学した私にとって、アメリカは自由と民主主義の国だった。誰もが平等にチャンスを与えられる場所。貧しくても虐げられていても、死と隣り合わせの暴力が日常を支配していたとしても、海を越えこの国にたどりつきさえすればいい。そこに行けばアメリカンドリームという言葉がディズニーの魔法の粉のように降り注ぐ国アメリカ。
しかもそうした人々と私の間には決定的な違いがあった。
橋を焼くような思いでアメリカを目指す彼らと違い、私には何かあればいつでも帰ることのできる祖国があった。一億総中流で、ワーキングプアやネットカフェ難民という言葉も氾濫しておらず、学校を出て就職するのが当たり前で、うまくいけば結婚出来てマイホームを持てる。健康保険や退職後の年金が誰もに約束されていて、餓死や行き倒れになる心配もなく、二十代三十代の若者たちは元気いっぱい「自分探し」さえしていればよかった。
そんな日本の存在が、あの頃同じように海外に出た多くの日本人留学生にとってどれだけ支えになっていたことだろう。たとえ意識していなかったとしても、見えない毛布のように、どこかで柔らかく心が守られていたように思う。
そう、守られているものにとって、「動物農場」は最高のエンターテイメントになる。あの時「こういう作品は独裁国家でこそ観られるべきだ」といったマシューの言葉を思い出し、私は不思議な気持ちになる。何故ならこの内容は、本当に観られるべき場所では決して観られる事がないからだ。
あの時のマシューは私と同じ、守られた側の人間だった。彼は動物たちがファシズムに落ちていった大きな原因は、指導部である豚たちにとって都合のいい情報ばかりが流されたせいだと指摘していた。情報操作は独裁的な豚であるナポレオンの過剰な権力誇示や、暴力的な犬達の監視システム、見せしめとしての反逆者への容赦ない制裁など、恐怖政治になっていることを全く気づかせない程巧妙になされ、動物たちを感覚麻痺にさせたのだと。
民衆に真実を伝えることこそがファシズムを止める術だというマシューは大学卒業後新聞社に就職し、理想に燃えたジャーナリストになった。彼にとって憲法で保障された言論の自由こそ、アメリカ人であることの誇りだった。