Main Contents
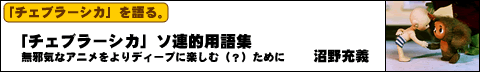
「チェブラーシカ」ソ連的用語集
─無邪気なアニメをよりディープに楽しむ(?)ために
沼野充義 (ロシア・東欧文学者)
「チェブラーシカ」のようなアニメは、社会的背景の説明抜きにその可愛らしさを楽しめばいいのであって、実際、この作品が作られた当時のソ連の事情など知らなくてもいっこうに差し支えない。しかし、現代の日本人にはわかりにくいことも多いから、と編集部から依頼を受け、若干無くもがなの説明を試みることにした。そして実際にこの文章を書いて問題を整理してみると、予期していた以上のことがこの一見無邪気なアニメには含まれていることが改めてわかって、私自身にとっても面白い発見の連続になった。というわけで以下は、「チェブラーシカ」をよりディープに楽しむ(?)ためのソ連的用語集といったところである。気になる項目だけでも拾い読みしていただければ、と思う。
オレンジ
旧ソ連時代、一般市民は日常的な消費物資の不足に悩まされ、新鮮な野菜や果物を手に入れるのもままならない、ということがしばしばだった。ソ連は宇宙開発ではアメリカに先駆けて一九六一年に世界で最初の有人宇宙船を打ち上げるのに成功したくらいだから、科学技術の水準は決して低くなかったのだが、普通の人たちの生活に必要なものが足りない、という不思議な国だったのだ。特に冬場は、新鮮な生野菜を確保するのが北国のロシアでは難しく、料理の付け合せはせいぜいキャベツやビーツ(赤カブ)の酢漬け、それにジャガイモばかりという単調なメニューになりがちだった。
だから、南国の新鮮なフルーツは、旧ソ連時代の人々にとって、特別輝かしいものに見えた。バナナやオレンジ、さらにコーヒー豆などは、ロシアでは栽培されないので、外国からの輸入に頼らざるを得ない。しかし、東西冷戦時代にソ連がこういったものを輸入できたのは、アジア・アフリカや中南米の親ソ的な国からだけだった(オレンジの最大の産地はアメリカ合衆国だが、もちろん、ソ連がアメリカからオレンジを輸入することはできなかった)。当然、こういったものは店頭で見かけることなどめったにない贅沢品となり、たとえばアフリカから輸入された新鮮なオレンジがどこかで売られている、などということがわかれば、人々はそれを買うため店に殺到し、一種の「祝祭」的な賑わいを呈することさえあったようだ。
例えば、旧ソ連で人気の高かった作家ワシーリイ・アクショーノフには「モロッコのオレンジ」という中篇小説(一九六二)がある。厳しい冬のある日、ソ連の極東の港町に、モロッコからのオレンジの積荷が到着する。これは寒気に封じこめられた地方都市に暮らす人々にとって、ちょっとした事件だった。町は一種のカーニバル的な興奮状態になる。その雰囲気が、五人の若者たちの交錯する視点から、祝祭的に描きだされていく。当時のソ連の若者文化の代表者であり、前衛的な小説の書き方を実験していたアクショーノフならではの傑作だが、オレンジがそれほどの貴重品であった時代背景を知らないと、ちょっと理解しにくい作品かも知れない。われらのチェブラーシカもまさに、そのオレンジの積荷とともに寒いロシアにやってきた。だから、チェブラーシカにはソ連の灰色の日常を打ち破る、祝祭的な贈り物の要素がその出自から備わっていたのである。
友だち
 孤独なワニのゲーナが「友だち募集」の貼り紙をすると、その呼びかけに応じて、犬や少女やチェブラーシカが集まってきて、彼らはいっしょに力を合わせて「友だちの家」を作ろうとする。この背後に集団主義的なソ連のイデオロギーがあるとまで言ったら興ざめかもしれないが、もともとロシアには共同体志向の強い国民性があった。動物たちがいっしょに力を合わせて「うんとこしょ、どっこいしょ!」と掛け声をかけながらカブを引き抜くという、有名なロシア民話「大きなカブ」を思い出せばいいだろう(これはソ連体制の成立以前から伝わる古い民話なのだが、ソ連の共産主義の宣伝だと思いこんで、とんちんかんな批判をした政治家が日本にはいて、ちょっとした議論を呼んだことがある)。
孤独なワニのゲーナが「友だち募集」の貼り紙をすると、その呼びかけに応じて、犬や少女やチェブラーシカが集まってきて、彼らはいっしょに力を合わせて「友だちの家」を作ろうとする。この背後に集団主義的なソ連のイデオロギーがあるとまで言ったら興ざめかもしれないが、もともとロシアには共同体志向の強い国民性があった。動物たちがいっしょに力を合わせて「うんとこしょ、どっこいしょ!」と掛け声をかけながらカブを引き抜くという、有名なロシア民話「大きなカブ」を思い出せばいいだろう(これはソ連体制の成立以前から伝わる古い民話なのだが、ソ連の共産主義の宣伝だと思いこんで、とんちんかんな批判をした政治家が日本にはいて、ちょっとした議論を呼んだことがある)。
そう言えば「友だちの家」という呼びかたにもちょっとロシア的というか、ソ連的な響きがあることを指摘しておこう。「~の家」というのは、ソ連では職業組合や組織などの「会館」の意味でごく普通に使われたタイプの名称だからである。
ところで、ここでワニのゲーナが呼びかけ人となった友だちの輪には、犬のトービクや女の子ガーリャといった普通のロシアの動物や人だけでなく、ライオンやチェブラーシュカ、キリン、サルなど、エキゾチックな南国の動物たちが入ってくることに注目しよう。子ども向きの童話だから、動物園の人気者たちが総出演してももちろんおかしくはないのだが、南国のエキゾチックな動物たちがみな「友だち」だということになると、やはりそこにソ連のイデオロギー的背景を見ないわけにはいかない。というのは、アメリカを筆頭とする資本主義国と対立しながら、アジアやアフリカの多くの国々を「友だち」とし、これらの諸国と「友情」を結ぶというのが、当時のソ連の基本的な外交姿勢だったからだ。モスクワに冷戦のさなかの一九六〇年に設立されたルムンバ記念民族友好大学(ルムンバはコンゴ独立の指導者の名前)は、アジアやアフリカからの留学生をソ連の「友だち」として積極的に受け入れるための大学だった。ちなみに、ライオンにはチャンドルという名前が与えられているが、これはインドを連想させるものだ(「チャンドラ」とはヒンドゥー神話の神の名前で、しばしば傑出した人物の添え名とされる)。
外国のスパイ
もちろん、外国人がすべて「友だち」というわけではない。いつも皆の邪魔をする悪役として登場するのが、ネズミを子分として連れ歩くシャパクリャクという正体不明の女で、どことなく外国人風である。実際、ウスペンスキーの原作では、彼女は紙つぶてを口に詰まらせて診療所に駆け込むのだが、口が詰まっていてうまく話すことができないため、医者に外国人扱いされてしまうのだ。そもそもシャパクリャクというのは、オペラハット(折りたためるシルクハット)のことで、もともとフランス語のchapeau claque(シャポ・クラック)から来ている。名前からして外国語風なわけだが、この名前はさらに、ロシア語で女スパイを意味する「シュピオンカ」という単語に音がちょっと似通っている。
皆が力を合わせて何かをやっていると、それを妬んで妨害する人物が出てくるというのは、ハリウッド映画などにもごく普通に見られる、プロット構成上の紋切り型の一種であって、ソ連だけのものではないが、その妨害者が外国人風だということになると、やはりソ連的なイデオロギーの影響が感じられると言わざるをえない。ソ連の発展を腐敗した資本主義国が邪魔する恐れがある、というのは、建国以来、ソ連がパラノイア的に抱き続けてきた危惧であり、実際、典型的な社会主義リアリズム小説では、建設現場や工場に外国の手先が潜入して妨害工作を行うというのがほとんど定型になっていた。また第二次世界大戦中も多くのソ連市民が「ドイツのスパイ」とか「日本のスパイ」(!)として逮捕・処刑されたものだし、「チェブラーシカ」の第一話から第三話が作られた一九六〇年代から一九七〇年代でさえも、ソ連の一般市民にとって外国人は警戒すべき存在であって、見知らぬ外国人と気軽に口をきくことなど問題外だったのである。
ピオネール
第二話でチェブラーシカとゲーナが入団したいと憧れるピオネールとは、九歳から十四歳までの少年少女の組織で、ソ連版のボーイ・スカウト/ガール・スカウトと言えるだろう(ソ連のピオネールは男女の区別をしなかった)。その名称は「開拓者」の意味で、フランス語のpionnier(ピオニエ)から来ている(英語の「パイオニア」に同じ)。ただし、ソ連の場合は非常にイデオロギー的色彩が強いのが特徴で、革命の指導者レーニンの教えを守って、祖国を愛し、守ることを誓わされた。学校を基盤としてほとんどの子どもたちがピオネール組織に入らされたので、エリート集団というよりは、イデオロギー的な大衆組織であって、子どもたちが皆、ピオネールに憧れたとは思えないし、入団の資格がそれほど厳しく審査されたわけではないが、たとえばピオネールのシンボルである独特の赤いネクタイを締めた姿は、西側で子どもたちがボーイ・スカウト/ガール・スカウトを「カッコいい」と思う程度にはやはりカッコいいものだったのだろう。またピオネール組織は全国的にサマーキャンプ施設を持っていて、例えば南の保養地クリミアの「アルテク」というキャンプは最高のレベルの有名なもので、ここで夏休みを過ごすのは特権的なことだった。
ピオネールは様々な社会奉仕活動をすることになっていて、その中には金属屑の回収もあった。戦時中に金属を回収して武器製造に充てようとしたのは日本も同じことだが、ソ連では戦後も長い間、資源不足に悩まされ、金属屑や古紙の回収が盛んに行われていた。宇宙にロケットを飛ばす一方で、基本的な物資が不足しているという、矛盾に満ちた社会だったのだ。アニメの中に出てくる「すべての不要なものをスクラップに! 金属屑を集めよう!」という言葉は、当時のソ連で実際によく聞かれたスローガンである。
十四歳になってピオネールを終えた子どもは、さらにコムソモール(共産主義青年同盟)に加入することを期待され、その中のエリートが共産党員となって、ソ連の特権階級を構成した。つまりピオネール⇒コムソモール⇒共産党というのは、普通の学校教育と並行して共産党の直接指導のもとに敷かれたもう一つのレールだった。
環境汚染
 第三話では川に排水を垂れ流す工場が登場し、ゲーナは平然と環境を汚染する工場長に敢然と立ち向かう。旧ソ連にもこのような環境問題があったのか、と意外に思われる向きも多いのではないだろうか。実際、ロシアは膨大な土地や資源を持つ超大国であり、多少の排水やゴミで環境が汚染されることなどないだろう、とのんびり構える人たちはまだ多かったはずである。そのうえ、イデオロギー的にいうと、公害というものは資本主義社会において私企業が利潤をむやみに追求した結果生じるもので、生産手段が国有化された社会主義国では起こりえない、とする公式的な考え方が、当時はまだソ連国内だけでなく、西側の知識人の間にも強かった。
第三話では川に排水を垂れ流す工場が登場し、ゲーナは平然と環境を汚染する工場長に敢然と立ち向かう。旧ソ連にもこのような環境問題があったのか、と意外に思われる向きも多いのではないだろうか。実際、ロシアは膨大な土地や資源を持つ超大国であり、多少の排水やゴミで環境が汚染されることなどないだろう、とのんびり構える人たちはまだ多かったはずである。そのうえ、イデオロギー的にいうと、公害というものは資本主義社会において私企業が利潤をむやみに追求した結果生じるもので、生産手段が国有化された社会主義国では起こりえない、とする公式的な考え方が、当時はまだソ連国内だけでなく、西側の知識人の間にも強かった。
しかし、一九六〇年代から七〇年代にかけて、それは建前だけの幻想だということが次第にはっきりしていった。ソ連ではもともとスターリン時代以来、「計画経済」の数値目標を達成するために、しばしば消費者のニーズや生活環境を無視して工業化が進められてきたが、その結果、一九六〇年代には様々な問題が噴出し、ショーロホフなどの著名な作家たちも抗議の声を上げ、共産党も環境保護に取り組まざるを得なくなっていった。特に深刻な問題になったのは、パルプ工場のせいで、アジア最大、世界最深の巨大なバイカル湖が汚染されたことである。一九八〇年代には作家のラスプーチンがバイカル湖の環境保全のための運動を展開し、一九八九年には彼を招いて日本で琵琶湖フォーラムが開催され、環境汚染がもはや資本主義や社会主義といった制度を超えて世界共通の問題であることが明らかになった。
「チェブラーシカ」で環境汚染が取り上げられているのは、それだけ当時のソ連で問題が深刻になりつつあったことを意味している。子ども向きのアニメでさえも、時にはこのように風刺や社会批判の機能を果たすことがあるのは、さすがソ連と言うべきだろうか。しかし、この批判にはもちろん限界もあった。第三話でも「悪玉」として描かれるのは結局のところ、工場長個人であって、批判の矛先は、こういう公害を生み出す本当の元凶、つまり社会的な構造や共産党の支配体制そのものに対してはなかなか向わない。
「修理中」と働かない労働者
環境汚染問題に次いで、第四話でも社会問題が取り上げられる。それはいたるところ「修理中」でまともに機能しない設備や施設、そしてまともに働かない労働者の問題である。アニメの中にも何度か登場する「РЕМОНТ」という看板は、ロシア語で「修理」「改築」などを意味するものだが、実際には「故障中」「閉鎖中」の婉曲な言い換えであると考えたほうがわかりやすい。当時のソ連ではいたるところにこういった掲示を見かけたものだが、それではどのくらいきちんと修理が進められているのか、劇場や学校が「改築」をいつ終えて再開されるのか、となると、まったくわかったものではなかった。その背後には、小回りがきかず人々の日常的な必要に迅速に応えられない非能率な社会主義経済と、まともに働こうとしない労働者の問題があった。
第四話では始業式を明日に控えているというのに、「改築」中のはずの学校の中でトランプに興じていて仕事をしない労働者たちの姿が風刺的に描かれているが、それもそのはず、ソ連では労働者はきちんと働いたところで給料がよくなるわけでもなく、競争原理など存在しなかったから、労働者も勤め人もさらには研究者でさえも、勤労意欲をなくし、職場でだらけていても、飲酒にふけってろくに仕事ができなくても、平気だったのだ。当時の一種の皮肉な決まり文句に、「国家は(給料を)払う振りをし、人々は働く振りをする」というのがあったほどだ。またこの頃よく聞かれた一口話には、例えば、アメリカの労働組合の代表者がソ連の工場を訪問したとき、仕事時間だというのにろくに働かないソ連の労働者の姿を見て勘違いし、「皆さんのストライキを支援します!」と叫んだ、といった類のものがある。もちろん、当時のソ連で労働者が共産党体制に抗議してストライキをすることなど、考えられなかった。
悲しい歌と「転ぶ」こと
このように見てくると、単純で無邪気なアニメのように思える「チェブラーシカ」にも、ソ連特有の社会的背景やイデオロギー的なバイアスがあることがよくわかる。そういったことを知ったからといって、このアニメがより楽しめるようになるかどうかはわからない。しかし、この作品がより複雑な陰影を帯びてくることは確かだろう。環境汚染や労働者の怠慢といった社会問題に対するかなり辛辣な風刺になっていることも、現代の日本人には意外な「ソ連的」側面と言えるかもしれない。共産党支配のもとに厳しい検閲が行われ、言論の自由が抑制されていたソ連で、このような風刺があったことに驚く人も少なくないのではないだろうか。日本ではあまり知られていないことだが、ブラックユーモアのきいた一口話や風刺小話は、ソ連で特に発達したジャンルであり、人気の高い風刺漫画の専門誌にまさに『クロコディール』(ワニ)と題されたものがあったほどである。
しかし、そういった風刺は(「チェブラーシカ」の場合ももちろん)、検閲に許される範囲内のものであって、先ほど述べたように、共産党支配体制の根幹を批判するところまでは行かない。そうだとしたら、この程度の生ぬるい風刺は無意味ではないのだろうか? 誤解を避けるため強調しておきたいのだが、私はそんなことを言いたいわけでは全然ない。
前にも何回か見ている「チェブラーシカ」を今回、この原稿を書くために改めて見て感じたのだが、このアニメが時間も空間も隔たった現代日本の大人の心をいまでも打つとすれば、それはその無邪気な可愛らしさにもまして、ここに漂うもの悲しさゆえではないだろうか。例えばゲーナが第二話で歌う「誕生日の唄」、第三話で歌う「青い列車」は、どちらも一度聞いたら忘れられないような親しみやすいメロディの曲だが、同時になんとも言えないさびしさをたたえている。「青い列車」には前途には「よりよい」ものがあって、皆それを信じたいのだ、という言葉があるが、「よりよい未来」という共産主義の公式的建前であったはずのものが、ここでは勇ましく唱えられるのではなく、平凡な庶民の生活感に寄り添うものとして現れる。つまり、「チェブラーシカ」にとって大事なのは、それが官許の枠のなかでどの程度社会批判に成功しているかといったことではもちろんなく、大げさな建前論や美辞麗句で塗り固められた政治的宣伝に与せずに、「ちっぽけなさびしい人間」の本音の立場に立って物事を見ている姿勢そのものにあるのだ。これはやはり同じように「ちっぽけな人間」の哀歓を歌って、同時期のソ連で国民の圧倒的支持を得た吟遊詩人ブラート・オクジャワにも通じるものだろう。ちなみに、「チェブラーシカ」とは、語源的に「転んでばかりいるもの」「倒れるもの」といった意味だが、ぐらぐらしながら、時に転んでもなんとかやっていくというのは、まさに普通の人間の生き方そのものではないか。それは共産主義の理想を信じ、転ばないでまっすぐ突き進むヒーローの対極にあるものだ。
沼野充義(ぬまの・みつよし)
一九五四年、東京都生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科教授(現代文芸論・スラヴ文学)。一九七七年に東京大学教養学部を卒業後、ハーバード大学大学院に留学。ワルシャワ大学東洋学研究所講師、モスクワ大学アジア・アフリカ研究所客員講師などもつとめる。著書『徹夜の塊 亡命文学論』でサントリー学芸賞、『徹夜の塊ユートピア文学論』で読売文学賞を受賞している(いずれも作品社刊)。









