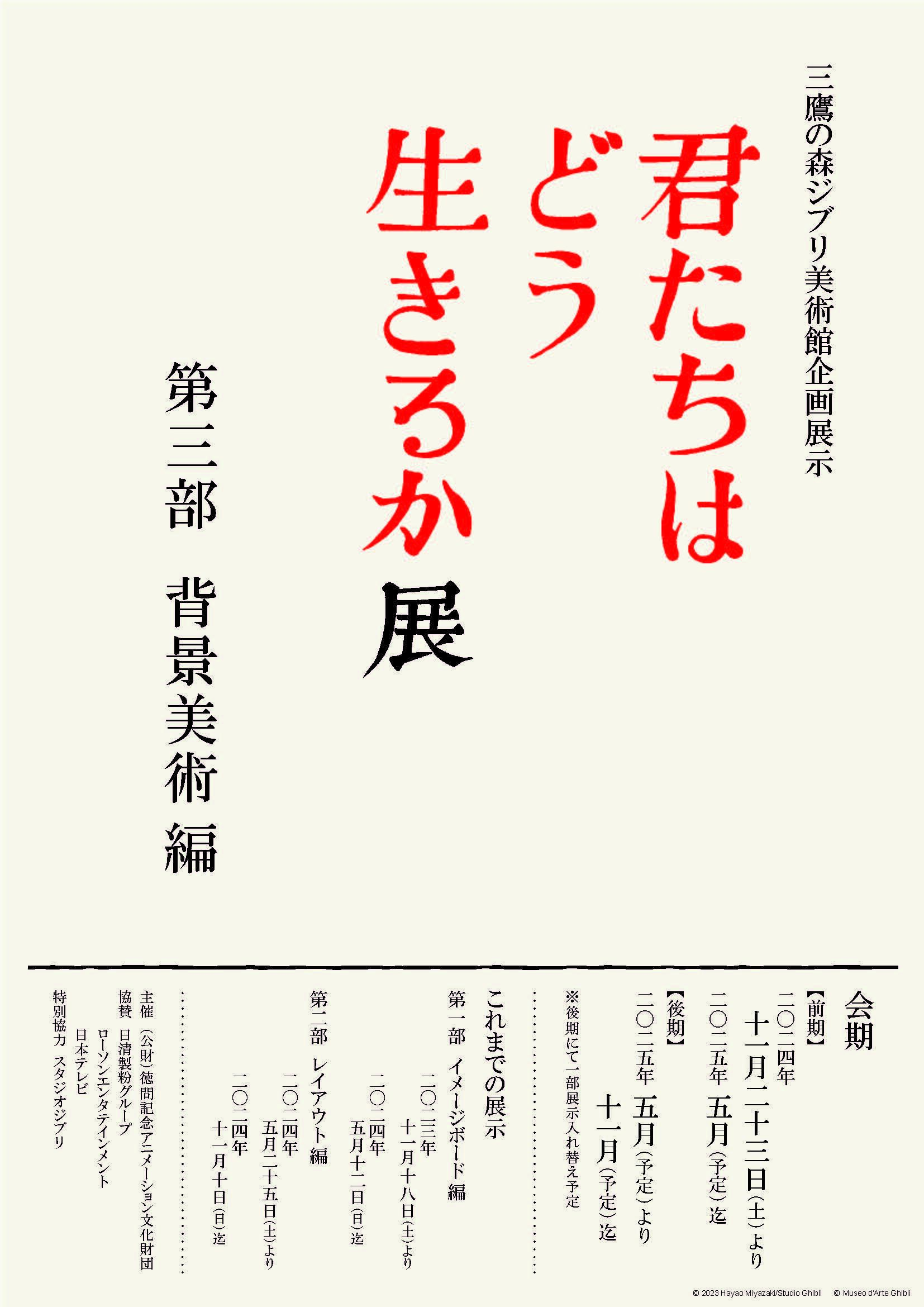西岡事務局長の週刊「挿絵展」 vol.33 ぼくの妄想史【壱】 ウォーターハウスから始まる
2013.01.17
今回から、この企画展のある意味、目玉でもある、"ぼくの妄想史"というコーナーで展示されている絵画について考察を重ねてみたいと思います。ここで取り上げられているのは、まさに宮崎監督自身が考える、本の挿絵を始まりとした、通俗文化にまつわる美術史です。ただ、"妄想史"とあるので、専門家が完全に裏づけを取った美術史というよりは、宮崎監督による自由な想像の創作と言えるでしょう。ただ、同じ作家であるからこそ感じられる説得力のある内容なので、今回の展示ではもっとも監督のカラーが出ていて、見ごたえのある内容と思うのです。
2006年2月、宮崎監督は渡英しました。目的は、タインマスのブルックランズ博物館を訪ねるためでしたが、同時に100年以上前に英国留学した夏目漱石の足跡をたどる目的もありました。その際、訪れたのがロンドンのテムズ川畔に建つテート・ブリテン(Tate Britain)です。この美術館は、イギリス美術を体系的に収集展示している美術館で、なかでも、ラファエル前派の絵画については、そのほとんどを収蔵しているのだそうです。有名なミレイの「オフィーリア」(Ophelia)もウォーターハウスの「シャロットの女」(The Lady of Shalott)も、この美術館を代表するコレクションです。
その際、宮崎監督はこの美術館を訪れ、当時読み込んでいた夏目漱石の作品にも登場するこの二つの絵と対面し、衝撃と深い感銘を覚えたのだそうです。その時の気持ちは、のちのテレビ番組のインタビューで次のように述べられました。
「なんだ。彼らが全部やってたことを、下手くそにやってんだって思ったわけ。ああ、おれたちのアニメーションは今までやってきた方向でこのまま行ってもやっぱりダメだって。おれはもう、これ以上行きようがないって感じてる」
美しく丁寧な自然描写で、隅から隅まで背景描写に力を入れる。写真と見まごうばかりの精密さは、周囲の空気感まで表現し、見るものの目を釘付けにして離さない。描かれるヒロインの嘆きや絶望は画面を通してひしひしと伝わってくる。このような描写を、アニメーションの画面作りでも目指していました。ただ、それは100年も前の画家たちにより達成されていて、さらにその完成度は比類ない。その衝撃が宮崎監督を襲ったのです。
一本の作品で1000枚以上の背景画を必要とするアニメーション映画と、何ヶ月もかけて完成させる画家の渾身の一枚とを同列に扱うのはずいぶん乱暴な気がしますが、作品を生み出す監督にとって、世の中に発表される自分の作品という意味では同じなのです。そこに理想の作品が先人の手によって生み出されていたという事実は、あまりにも衝撃的でした。
この「シャロットの女」という作品は企画展の展示でも写真をみることができます。あたかも写真のような精巧な絵ですが、そこに描写されている女性のしぐさ、水面の映り込み、水草の角度、船に立てられた蝋燭の炎の全てが作者によって綿密に計算された描写なのです。写真でこれを再現しようとしても何千枚撮っても作者の完全に思い描いた瞬間を切り取ることはできないでしょう。これが、絵画と写真の大きな違いです。写真はもっと偶然性に依存していて、それが思いも因らない傑作を生み出すことがあり、面白さともいえるのですが。(この違いは、映画におけるアニメーションと実写の違いにも当てはまります。宮崎監督は、偶然性に因らないアニメーションの道を選んだのですから、その作品に対する姿勢がうかがえると思います)
こうした、100年以上前のウォーターハウスやミレイの作品に自分たちの作品の目指す世界を感じてしまったところから、本当の"ぼくの妄想史"が始まるのです。

"「挿絵が僕らにくれたもの」展-通俗文化の源流-"は5月20日までの開催です