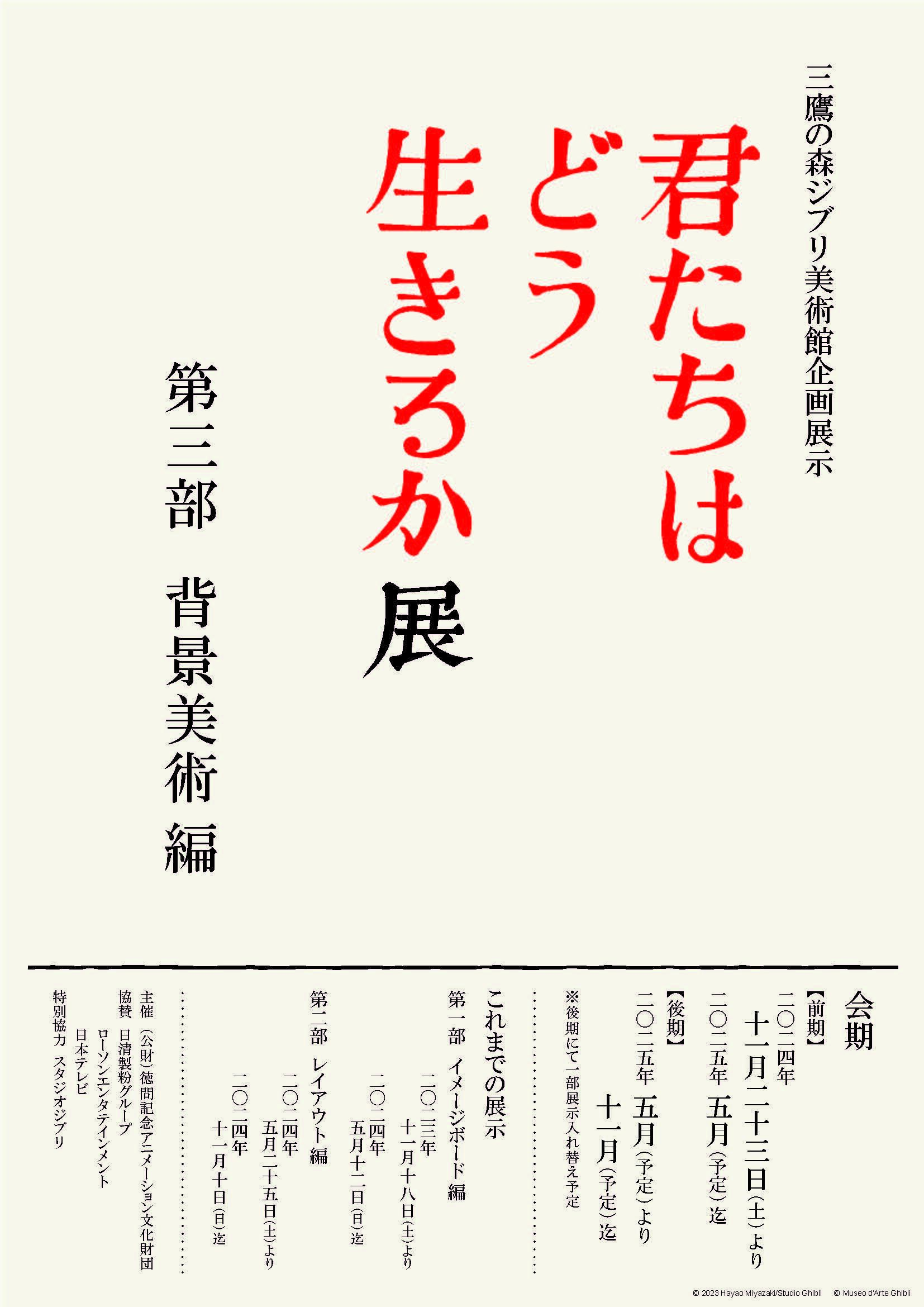西岡事務局長の週刊「挿絵展」 vol.38 ぼくの妄想史【六】 夭折の天才画家が狙ったもの
2013.02.19
青木繁は、わが国を代表する近代洋画家です。1882年に福岡県久留米市の下級武士の家に生まれた繁は、幼少の頃から学問の才能を発揮し、周囲からは文武のみならず芸術にも秀でた神童として注目を浴びます。小学校ではのちに日本を代表する画家として成功する坂本繁二郎と出会い、これまで誰にも負けたことのなかった繁が美術ではじめて敗北感を味わいます。そのこともあってか、中学に進学してからは文学への道へ歩もうと模索を始めるのですが、そのことで学問の成績が振るわなくなり、もう一度美術家への道に戻ることになり、卒業後、東京美術学校に入学し、黒田清輝から洋画の洗礼を浴びることになるのです。それからは、洋画家として活躍を続け、日本で初めて国の重要文化財に指定された代表作「海の幸」(1904)を発表するのですが、持ち前の激しく奔放な性格のため放浪生活を続け、1911年、肺結核のため28歳の短い生涯を終えました。
今回の企画展で取り上げられているのは、そんな青木繁のもうひとつの代表作「わだつみのいろこの宮」(1907)です。青木繁が晩年(といっても25歳なのですが)に古事記の「海彦山彦」から題材を取り、中央画壇での名声を狙って東京勧業博覧会という展覧会に応募するのですが、三等末席という結果に終わり、その結果に憤慨、失望して、放浪生活に身を落としていくことになるいわく付きの大作なのです。
この作品は、これまでの青木繁の作品とは少し趣を異にしているように思います。「海の幸」(1904)や「大穴牟知命」(1905)のもつ激しさが影を潜め、筆致が落ち着いており、構図や細部への書き込みもなされた精緻な作品となっています。これを見て、宮崎監督は「"ラファエル前派"の影響がある」と感じたのかも知れません。確かに、その描き込みと精密さは、これまで紹介してきたラファエル前派の先人たちの作風に通じるものがあるといっても過言はないでしょう。この作品はたまたま博覧会会場に来ていた夏目漱石の心をつかんだものと見えて、小説『それから』の中で主人公に「青木という人が、海の底にたっている女の人を描いたが、あれだけが、よい気持ちに出来ていると思った」と語らせているところにも現われています。漱石もラファエル前派の絵画を好んでいたのですから、この青木の絵に心惹かれたのは、宮崎監督と同じです。ただし、漱石の方が100年以上前になんですが。
「ぼくの妄想史」コーナーで、この「わだつみのいろこの宮」の横に比較される作品として並んでいるのが、ラファエル前派に属する画家、トーマス・アームストロングの「カラーの花を持つ婦人」(Woman with Calla Lilies, 1876)です。随分と題材が違いますが、確かに婦人の衣装が、「わだつみのいろこの宮」の侍女(右下の女性)にそっくりです。このふたつの絵が似ているかどうかは別として、青木が当時の画壇で認められるために、あえてラファエル前派の画風を取り入れた絵を描いたのかもしれないという事実は覚えておいてもいいと思います。ただ、この推論もすでに"妄想史"の範疇に入っているかもしれませんが(笑)

これまで、何回かにわたり、明治期になって洋画が日本に一斉に入ってきて与えた影響の大きさを述べてきました。宮崎監督曰く「近代日本の芸術絵画は、西欧の新しい潮流を追うのに忙しく、席の温まるヒマもなくなっていくのです」と。その中心はフランス絵画とイギリス近代絵画でした。そんな中で、キーマンとなる夏目漱石が英国留学し、日本に文化を持ち帰って作品に反映させたことは、西欧の文化が日本に定着し、変容していった過程に大きな影響を与えたといえるのです。そんな話題が次回からも続きます。