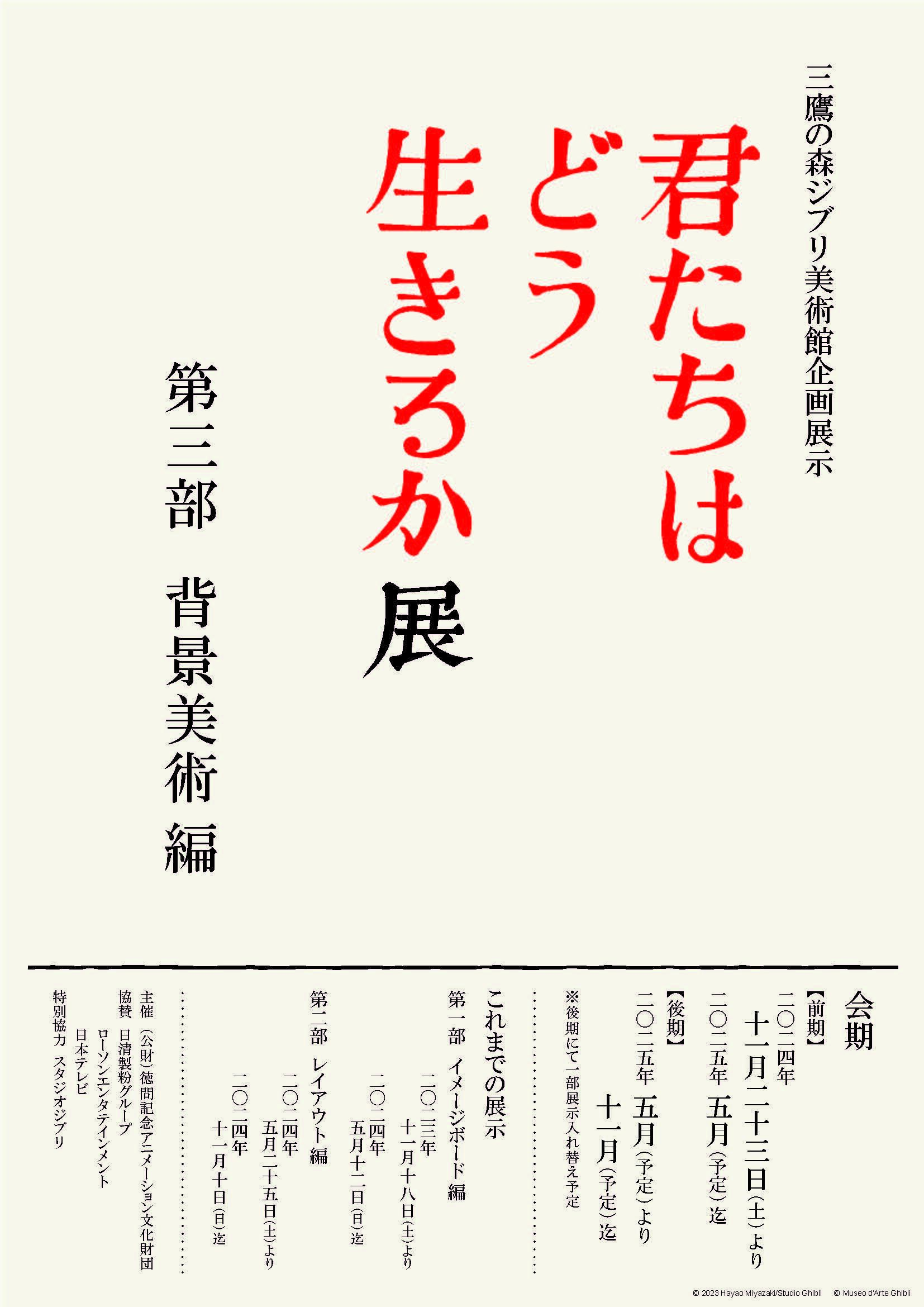西岡事務局長の週刊「挿絵展」 vol.41 ぼくの妄想史【七】 忘れられた人気挿絵画家
2013.03.12
今週は、ついに「ぼくの妄想史」シリーズの最終回です。明治から大正にかけて、大変人気のあった挿絵画家、鰭崎英朋(ひれざきえいほう,1880-1968)を紹介したいと思います。鎖国が終わり明治の世になって、怒涛のように西欧文化が押し寄せ、日本人はそれをキャッチアップしようと必死でした。美術界でもフランスやイギリスから洋画がもたらされ、それまで主流だった日本画を捨て、洋画の道を選んだ画家たちがたくさん生まれたことは、これまでの連載で述べてきたとおりです。ただ、その画家たちが西洋の模倣から自らのアイデンティティを確立しようと試行錯誤していたのに対し、通俗文化寄りの世界で活躍していた画家たちは、もっと自由に自らの作家性を開花させていました。そんな画家の一人が鰭崎英朋です。
鰭崎英朋は、本名を太郎といい、東京に生まれました。父親のいない家庭に生まれ、12歳で日本橋蠣殻町の履物商へ奉公に出されるのですが、奉公先の主人に才能を認められ、17歳で最後の浮世絵師と呼ばれた右田年英のもとに弟子入りします。20歳の時に2歳年上の鏑木清方とともに烏合会(うごうかい)を結成し挿絵画家として活躍を始めます。なかでも美人画の分野では、前述の清方と人気を二分する売れっ子として、人気は最高潮に達します。その後、鈴木清方が挿絵や浮世絵ではない"本絵"(大衆向きの版画ではない正統派の日本画)の道を選んだのに対し、英朋は、家族を養うために日々の仕事をこなす挿絵画家の道を選択せざるをえませんでした。現在、鈴木清方に比べ、鰭崎英朋の名がすっかり忘れ去られてしまったのは、彼が通俗文化の中で生涯を終えたからだといっても過言ではないでしょう。
鰭崎英朋は、膨大な仕事をこなしていました。小説や新聞、雑誌の挿絵はもちろん、1899年より東京朝日新聞紙上で、相撲絵の連載を始めます。当時は、写真もまだ普及していなかったので、新聞は、前日の相撲の取り組みの決まり手を挿絵として載せていたのです。各新聞がその相撲絵で競っていたのですが、英朋の相撲絵は、力士の表情や個性まで細やかに表現しているとの評判で、断トツの人気を誇ったのだったそうです。取り組みを毎日観察してスケッチした上で、翌日の新聞に間に合わせていたのですから、莫大な仕事量です。当時は現在と違って、年2場所、10日間ずつの取り組みしかありませんでしたが、この仕事を23年間も続けたのだそうです。しかしそれも、日々捨てられていく後世に残る仕事とはいえませんでした。
 "東京朝日新聞に掲載された相撲絵"
"東京朝日新聞に掲載された相撲絵"
また、彼は幽霊画も好んだそうです。そういう幻想怪奇趣味もあって、幻想文学の先駆者、泉鏡花との仕事も残されています。それが、この企画展示でも紹介されている下記の挿絵です。
 "『続風流線』(泉鏡花) 口絵, 1905"
"『続風流線』(泉鏡花) 口絵, 1905"
宮崎監督の解説によると、当時の挿絵は画家は線画だけしか描かず、その後は彫師と刷師に指示を出しながら最終的な作品に仕上げていったのだそうです。つまり、挿絵師とは原画マン兼監督の役割を果たしていて、どこか、現在のアニメーション制作にも通じる分業体制が出来上がっていたのです。
鰭崎英朋の名前は忘れられていましたが、近年になって一部で再評価が進み、回顧展も開かれるようになって来ました。作品の中には復刻されるものもあるようで、下記の講談社の「新・講談社の絵本」シリーズもそのひとつです。
 "講談社刊, 1,500(税抜き)"
"講談社刊, 1,500(税抜き)"
アニメっぽいデフォルメしたキャラクターではなく、見るものに強烈な印象を与える挿絵です。筆者も幼少の頃読んだ記憶があります。子どもだけでなく大人楽しめる絵本として、今だから読み返してみたいと思わせる一冊だと思います。
鰭崎英朋が挿絵画家としてがむしゃらに仕事を続けたのは、まだ見ぬ父親に再会するためだという話があります。自分が有名になることで父親が名乗り出てくれるのではないか、その日を夢みつつ仕事を続けたというのですから、心を打たれるものがあります。しかし残念ながら、88歳でこの世を去るまで、その日はやって来なかったそうです。