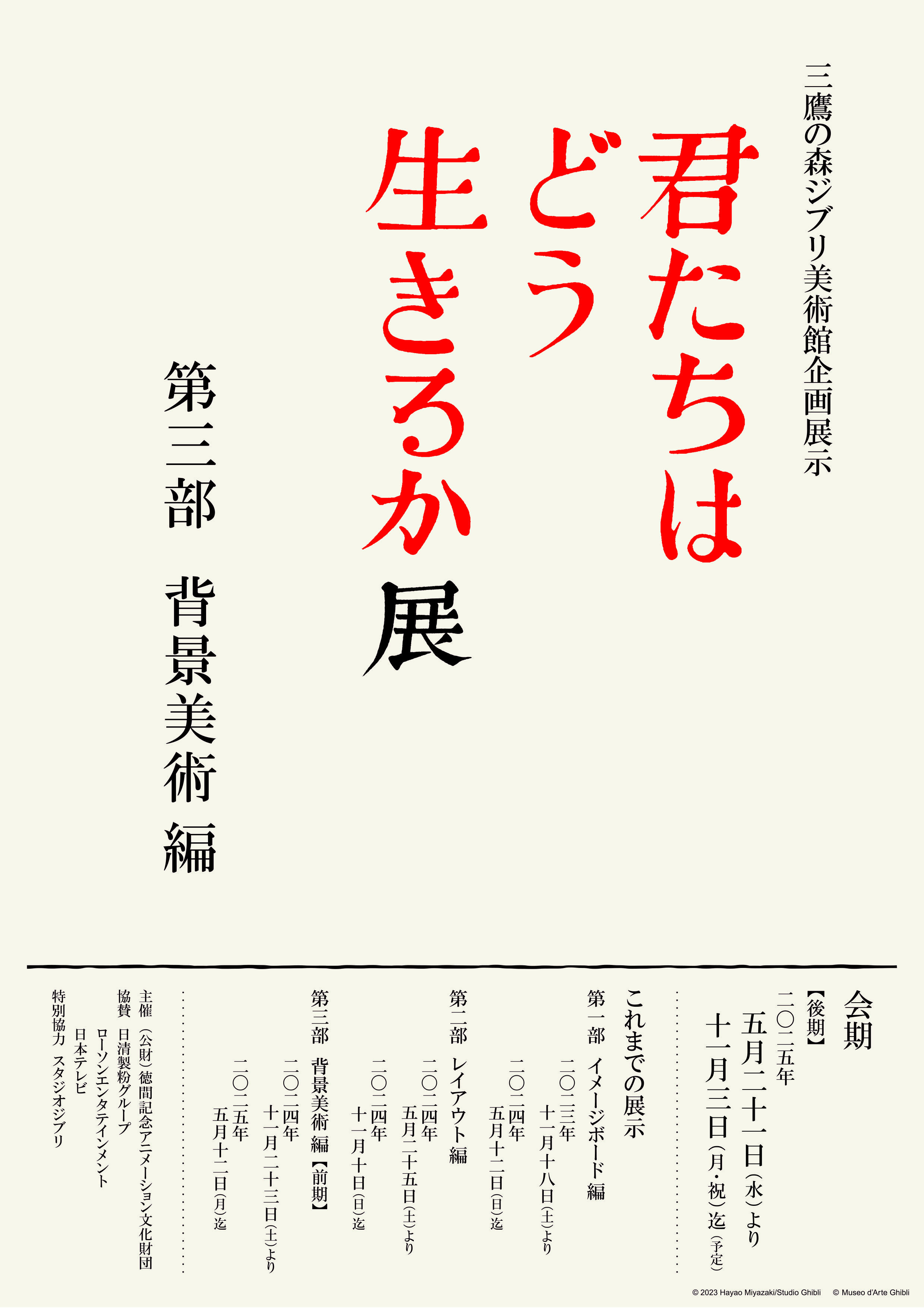西岡事務局長の週刊「挿絵展」 vol.42 通俗文化とは何か【壱】 ミュシャ展に出かけて
2013.03.19
連載も残すところあと9回となりました。前回の妄想史シリーズが終わって、今回の企画展について、その全貌の魅力をほんのさわりだけですが、お伝えすることができたと考えています。今回はタイトルに含まれている"通俗文化"の定義について、少し考えてみたいと思います。
"通俗文化"とはどう定義づけすればよいのでしょうか。辞書を調べると、"一般大衆にわかりやすく受け入れやすい、一般向きである文化"とあります。反対語は何なのでしょう。"芸術文化"がそれにあたるのでしょうか。また、大変近い言葉として、"大衆文化"という言葉が浮かんできますが、そのニュアンスは少し違うような気がします。この展示が始まる前、"通俗文化の源流"という言葉を"大衆文化の源流"としてはと、宮崎監督に進言したところ、「違う。"通俗文化"なんだ」ととても強いこだわりを持っていたことも思い出しました...。
そんなことを考えている最中、六本木の森アーツセンターギャラリーで開催中の「ミュシャ財団秘蔵 ミュシャ展」を見に出かけました。アルフォンス・マリア・ミュシャは、1860年に当時オーストリア領であったモラヴィアに生まれ、その後、パリで商業デザインの分野で大活躍し大人気を博したチェコ人のデザイナーであり画家です。菓子や石鹸の化粧缶や演劇のポスター、雑誌の挿絵など幅広い商業デザインを手がけ、その作品は100年以上経った現在でも流通しているものがあるほどです。ただ、1910年にチェコに帰国してからは、第一次世界大戦が勃発したこともあり、チェコ人の愛国精神を高揚させる作品を数々残し、1939年、第二次世界大戦が起こる直前に亡くなりました。彼の晩年は、公共施設に祖国の歴史を描いた作品を描いたり、切手や紙幣のデザインを手がけたりして持てるもの全てを祖国のために捧げたといえるでしょう。
そんな、ミュシャの数々の作品を見ながら感じたのは、その作品のモダンさと、現代にも十分に通じるデザイン性の素晴らしさでした。輪郭線を明確に描き、デザイン化された装飾で画面全体を飾る彼の手法は、現代のアニメーションや漫画の絵作りに通じるものが感じられます。また、作品を描く際、あらかじめモデルを写真に撮って、それを元に制作するところなど、明らかにそれまでの画家たちの制作手法とは異なっていると思います(当時の英国のラファエル前派の画家たちも写真を使っていたので、当時としてはごく当たり前なのかも知れませんが)。
これらの作品を見ていて感じることは、近代になって、急速に芸術作品と商業デザインの境界があいまいになってきたことでした。その違いは何なのでしょう。一般には、その作品が一点ものなのか、大量に複製されて広められるものなのかという点で区別するのでしょうが、一点ものだからといって、後世に残るほどの芸術性を持った作品だとは限りませんし、複製される印刷物や版画の中にも優れた作品が数多く存在するのはみなさんもご存知の通りです。また、アカデミーのような権威機関に認められた作品が"芸術作品"で、それからはみだしたものが"大衆作品"とも捉えられるでしょう。見るものに理解しやすいものが"大衆"で、教養がなければ理解できないものが"芸術"だということもできるかもしれません。ただ、ここまでくると、作品の存在意義さえ問われかねません。
いずれにせよ、20世紀になり高度な複製技術が発明されると、両者の境は至極曖昧になります。ミュシャの作品などはその典型ですが、この連載で取り上げてきた、通俗文化の担い手たちは全てがそうだといえるかもしれません。最早、アカデミーのような権威に守られ、貴族のようなパトロンに支えてもらって生活していける時代ではないので、芸術作品だけを制作していては食べていくのは難しい時代です。大衆向けに作品を発表し、人気を得ていくことも、芸術家の生きる術なのです。そう考えると、この連載で中心として取り上げてきた、ヘンリー・J・フォードやイワン・ビリービンなどは、新しい時代の芸術家だったと捉え直すこともできるかも知れません。
(この稿、続く)
 「ミュシャ財団秘蔵 ミュシャ展」2013年3月9日(土)-5月19日(日)森アーツセンターギャラリーにて開催
「ミュシャ財団秘蔵 ミュシャ展」2013年3月9日(土)-5月19日(日)森アーツセンターギャラリーにて開催
公式サイトはこちらからどうぞhttp://www.ntv.co.jp/mucha/