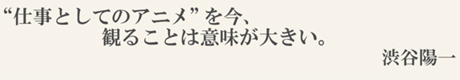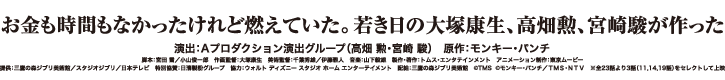Main Contents

誠実な仕事として作品を作るのが基本姿勢だと思うし、
実際にすぐれた表現の多くはそういう形で生まれてくる。
「ルパン三世」のテレビシリーズというのは宮崎駿さんや高畑勲さんにとってすごく大きな意味を持つと思うし、それと同時に、日本のアニメが育ってきた土壌やバックボーンみたいなものがすごくよくわかるような気がします。
それをひとことで言えば“仕事なんだ”ということだと思います。
宮崎駿さんという作家は、今や日本を代表する表現者であり、世界的にも認識されている偉大なアニメの演出家ですから、いわゆる文学者や音楽家や画家的な意味合いでのアーティストとしての地位までを手にしています。けれども、別に宮崎さん自身はそこを目的にしていないし、宮崎さんにとってのアニメというのもそういうものではないという気がします。宮崎さんはアニメが好きで、アニメをつくることに自分の職業としてのアイデンティティーを見出していただけなのではないのか─今回三本の「ルパン」を観て、そんなことを改めて感じました。
僕自身がやっているポップミュージックのフィールドでは特にそうなんですが、アーティストであるということに表現者としての優位性があるというような発想はありません。むしろそれはばかにされる。よく使う比喩なんですが、ビートルズはハンブルク時代、いわゆる売れない“箱バン”で、お客さんに見てもらいたいがために首から便器をぶら下げて演奏していました。それは芸人となにも変わりません。
あるいはブルースアーティストは、それこそ魂の叫びを求めて云々……みたいな後づけの物語がありますけれど、実際には頭に羽をくっつけて目立つ格好をしたり、あえてわいせつな歌詞を歌ってお客さんに喜んでもらったり、とにかく必死だったんです。そこで一杯の酒をもらい、その日暮らせる金をもらい……そういうことをやっていた人たちの音楽が、結果として、その当時アーティストだと言っていた人たちの作品の何千倍もアートなものであった─そういうことなんです。
だから、例えば新人バンドが写真撮影で「おれたちはロックをやりたいから、カメラ目線の写真なんて嫌だから」というようなことがあるとき、僕はよく言うんです。ビートルズは髪型を決められて、制服を着せられた。全員ユニフォームを着て、1曲終わるごとに頭を下げた。おまえらがビートルズより才能があるという自信があるんだったら言え。ビートルズ以下だと思うんだったら、ビートルズ以上のことを言うなと。
ようするに、ビートルズにとっても音楽をやるということは仕事だったんだと思うんです。何とか仕事にしたいという想いがあったし、今もすぐれた表現者たちは、まず誠実な仕事として創作活動をするというのが基本姿勢だと思うし、実際にすぐれた表現の多くはそういう形で生まれてきています。
もちろん、自分自身のライフワークを完成させるために、ひとり黙々と原稿用紙やキャンバスと向き合い、自分の表現みたいなものを追求する人たちもいて、それはそれなりのすぐれた作品を生んでいる部分もあるのかもしれないけれど、僕はそこにはあまり豊かな表現の結果というのが生まれてきていない気がします。というか、僕自身が興味を持つ表現が常に大衆的なもの、ポップなものであるという事があります。
今、日本が世界に誇っている表現であるアニメや漫画もそうですよね。すぐれた作家たちはすごく誠実に週刊誌連載やテレビシリーズと向き合ってきたと思うし、テレビの世界でも、一番知的に見えるのが芸人です。いわゆる文化人と言われている人たちよりも、たけしや松本人志のほうがはるかにたたずまいがすがすがしい。彼らはやっぱり「おれの表現が」とは言いません。自分たちの笑いをどれだけの人に受け入れてもらえるかという、その目線と視点がない限り、今の、いわゆる表現がマスで流通する社会状況の中で、すぐれた作品を生んでいくことなんてできない、とわかっているからです。
最初は東映動画で劇場用長編作品にかかわるところから始まっているにしても、マスという意味での出発点は、宮崎さんもまたそういうテレビのアニメというところが出発点なわけですから、当時は宮崎さんにとってのアニメがアートであるはずがありません。多くの人たちが仕事を選ぶのと同じような形でその仕事を選び、その中でどれだけすぐれた、誠実な仕事ができ得るかということに挑戦してきた人で、その中で幸福なことに怪物的な才能があったから、そこにとどまることなく、より彼自身の個人的な営為が大衆的な消費財としてもバリューを持ち、そして表現としても高いものになっていった。もちろん、心のどこかでは「いつかおれは長編アニメで自分のメッセージを」という想いはあったのかもしれないけれども、それが第一義ではなかったはずです。まずは仕事としてすぐれたアニメーターであろうとしたし、それゆえ、宮崎駿さんは唯一無二のアニメ表現者になり得た─僕自身はそんなふうに解釈しています。
宮崎さんはそういう姿勢でアニメーションに向き合われてきて、今や“世界の宮崎駿”になったにもかかわらず─なったからこそ、そこの姿勢を忘れていない。
なぜ常に宮崎駿さんのアニメがおもしろいのかというと、やはり基本的に“人々を楽しませる仕事である”という視点が絶対ぶれない。その、どこまでもポップであろうとする宮崎さんの原点がテレビアニメの中にある。
だから、今回の三本のルパンを観て思うのも「宮崎駿ってすごいよな。カット割りがやっぱりすげえ」ということではない。宮崎さんがその気になれば、もちろん、そういうあざといこともやれたと思うけれど、でも、ひたすらまじめにおもしろいアニメをつくっている。印象としてはとにかくおもしろい。特別とんがった表現なんてないわけで、ただ、驚くほどエンタテインメントとしてのクオリティーが高い。だから、三十年以上も前のテレビアニメで、それこそハード的な環境もものすごく悪いのにもかかわらず、全く古さを感じさせないし、飽きさせない。あざといことをやったら、きっと風化してしまったと思うんです。
なぜ鈴木プロデューサーは今「ルパン」を上映するのだろう。
僕はアニメ業界のことはよく知らないのであまり勝手なことを語れませんが、今、鈴木(敏夫)プロデューサーがこのアニメをわざわざ上映されるということは、もしかしたら、アニメがまずい方向に行ってるのかな、という推測が働いてしまいますね。
僕らのポップミュージック業界は長い歴史の中で、ポップであり、大衆的であり、音楽をやることが仕事であり、そこにおいてきっちりとした売れるものをつくるんだという姿勢が常識になってきています。昔、僕らが若かった時代にライブハウスなどによくいた、自分たちの演奏がうけない理由を「今日の客は悪いよな」みたいなことを言う─客が悪いんじゃなくて、おまえらのほうがつまんないのに─そういう人間は今ではほとんど見かけなくなりました。
でも、アニメは日本を代表する文化として世界から注目される中で、作家性や表現意識ばかりが先行しすぎて、仕事であるという基本姿勢がぶれているんじゃないか─鈴木さんはそんな危機感を感じているんじゃないかという気がします。みんなが宮崎駿や、あるいは押井守や庵野秀明になりたいと憧れるのはもちろん悪いことではないし、自分も「ナウシカ」を作りたい思う志はすばらしいけれど、おれは「ナウシカ」をつくるためにアニメ業界に入るんだというのは、それ、違わないか?─と。表現者とかアーティストとか言う前に、まず仕事なんだよと。そこができなくて何がアニメなんだと。
部外者である僕自身の無責任な実感としても、漫画や音楽の業界では、どんどん若い世代が出てきているにもかかわらず、アニメ業界ではあまりそういう状況がないようには感じます。相変わらず宮崎駿さんがトップを走り続け、あとは押井さんや庵野さんがいて、結局、この30年の歴史をふりかえれば宮崎さんと押井さんだけかよ、というのはメディアの人間としての素直な実感ですね。
最近はネットなどでマニアックな意見が交流するせいもあって、アニメを見る人が、だれだれの演出はすごいとか、あそこの動画はすごいというようなオタク的な思考が目立つようになってきたのも表現意識が先行してしまう一因だと思いますが、だれと向き合ってアニメを作っているのかということは大切ですよね。宮崎さんはそこで「子供に向けてつくるんだ」ということを執拗に繰り返している。それはやはり子供が最もシビアだからだと僕は思っています。子供はつまんないとすぐどこかに行ってしまうし、彼らには作家の名前も関係ない。つまり、勝負としては一番きつい勝負ですよね。
だから、今回上映される3本の「ルパン」が教えるものはすごく大きい。同時に、ひょっとすると失望する人もいるかもしれない。宮崎駿なんだから、高畑勲なんだからとんでもないことが行われているんじゃないかと期待して、「あれ、普通だな」と。「でも、おもしろいな」と。そこで、普通でおもしろいことをやるって、ひょっとするとものすごく大変なことなんじゃないのかなと。これをやれないで、普通じゃないとんでもないことをやろうといっても、それは無理なんじゃないか─そういうところに気づいてくれるといいですよね。
この三本の「ルパン」が放映された1971年当時、僕は大学生で、その翌年の1972年に仲間たちと『ロッキング・オン』を創刊しています。宮崎さんたちはいわゆる政治の季節に政治をやれた世代ですが、僕らは全共闘世代の後なので、終わってしまっていたわけです。高校時代には大学生たちが学校を封鎖しろとか何かわいわいやっていて、僕らも大学へ入ったらああやって石を投げるんだとか思っていたら見事に肩すかしを食らってしまった。そうした中で、自分たちが闘うところはロックしかなかった。だから、この世代はロックミュージシャンが多いんです。そのとき僕がロックに感じていた感覚─『ロッキング・オン』を作った感覚とおなじものを、宮崎さんのアニメにはいつも感じています。
だいぶ前にある雑誌のジブリ特集で答えたときにも、一番好きな宮崎作品で「もののけ姫」を選んで、その理由を「暴力性」と書いたんですが、僕は宮崎駿という人はロックだと思っています。その感覚は三十年以上前に作られた三本の「ルパン」にもすでに感じるし、最近公開された「崖の上のポニョ」でもまったく変わっていません。宮崎さんはとにかく世界を壊したい、焼き尽くしたいという思いですべてをやっている。世間が思っている宮崎駿と本物の宮崎駿は全然違うと僕は思っています。
だから、僕にとっての宮崎駿はロックスターとおなじで、その強烈な暴力衝動と破壊衝動を四十年以上も持続しながら、ここまでの大衆性を獲得し続けていることは、こんな時代だからこそ、見習うべきものが多いんじゃないか、と感じます。
きっと外からはわからないことですが、音楽業界というのはこの十年間、地をはうような構造不況の中で闘っています。レコード会社はリストラの嵐で、音楽雑誌もどんどんつぶれていって、あの会社つぶれたよとか、あのミュージシャンが契約を切られたよという状況が十年間以上も続いている。今社会が感じている危機感を十年前に我々は感じていて、今度は業界の危機に社会の危機まで相乗してきてしまったから、誰もが生き延びることで精一杯です。
つい最近も鈴木さんのラジオ番組(「ジブリ汗まみれ))にお招きいただいたとき同じような話をして、「ポニョだって前の作品より興行成績がいいのに上映できる劇場の数を途中で減らされる。今は映画の世界もそういう時代だ」というようなことをお聞きしました。そういう時期に─そういう時期だからこそ、三十年以上前に宮崎さんと高畑さんが無名の演出家として作られた“仕事としてのアニメ”を観ることは意味が大きいと、僕自身は思っていますし、“悪徳プロデューサー”(笑)の鈴木さんもきっとそんなことを思っているんじゃないでしょうか。 (談)
(音楽評論家 しぶや・よういち)
渋谷陽一(しぶや・よういち)1951年生まれ。明治学院大学卒業。大学時代からロック評論家として活動。1972年、ロック雑誌『ロッキング・オン』を創刊。現在は、株式会社ロッキング・オンの代表取締役社長。『CUT』『H』『SIGHT』などの雑誌を発行。ラジオ番組「ワールド・ロック・ナウ」のDJも担当。『風の帰る場所│ナウシカから千尋までの軌跡』(ロッキング・オン)では、自ら宮崎駿をインタビューし、本にまとめた。ほかにも北野武にも直接インタビューするなど「映画」ジャンルにも深くかかわっている。