メニュー
ページ内容
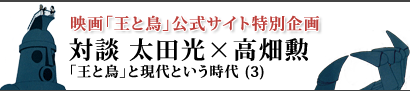
人間は言葉というものを 武器にするしかない
高畑
本当に太田さんの話には共感するんですが、相手の立場に立ってみたらどういう風に見えるんだろうか、思うだろうかという種類の想像力が、どんどん失われているのは明らかですね。それは身近な人間同士の付き合いから、国と国との関係でもそう思います。相手に対する想像力を、どうやってかきたてるかの問題だと思うんです。
司会
つまり物事は一方から見るのではなく、相対的に見ることが大事だと。「王と鳥」でも王様に反抗する鳥は、通常なら自由と正義の象徴なんでしょうが、そういう一方的な見方だけは括れない存在として出てきますよね?
高畑
確かに鳥は、王様に反抗する自由の象徴という一面があるんです。鳥は自由で、もしも空だけ飛んでたら、純粋に自由でいられるわけですね。ところが彼は地上のことに巻き込まれてしまう。地上に降りた鳥は、純粋に美しい心のままではいられないわけですよ。そして途中、王様に捕まって、足枷をはめられる。
その時、鳥はライオンがいる猛獣の檻に入れられるんです。彼はそこで詭弁を弄して、猛獣たちを暴動のために立ち上がらせる。そこだけ観ると革命劇のようだけれども、純粋とか正義とかというものではない。この物語は、絵の世界から抜け出た美しい羊飼いの娘を王様が横恋慕して追い掛け回すところから始まります。そして彼女は、王様に捕まる。鳥はここで猛獣たちに演説するんです。羊飼いの娘は丸々と太った羊を育てた。それは、誰のためか。あなたたちライオンのためなんだと。ところが王様が彼女を捕まえたために、せっかくの羊は世界に散らばって狼の食い放題になっている。この状況を皆さんは、どうしますかと言うんです。それを聞いたライオンたちは、暴動を起こして王宮へとなだれ込んでいくわけです。
ここでの鳥は正しいかどうかということではなくて、この状態になったらアジテーターにならざるを得なかった、というつらい現実を語っているんです。鳥の詭弁は正義じゃないけれど、物事は常に相対的であって、解釈ひとつではない。
たとえば、この映画に描かれた縦型社会の中で、観ている人間は自分をどの位置に置くか。おそらく一番下の下層市街にいる虐げられた人間でもなく、王様でもなく、もっと途中にいる人間だと感じると思うんですよ。そういうことから、王様に対してでも、虐げられた人に対してでも、鳥に対しても、自分は一体どういう位置にいるんだろうということを考えざるを得なくなって来てしまう。そういった映画なんですね。
司会
“気をつけたまえ。この国は今、罠だらけだからな”と映画のコピーにもなっていますが、常にいろんな視点でものを見るっていうことも考えさせるということですね。
太田

僕らは映画でも何でも、どちらかというと人ごととして見たくなるわけじゃないですか。例えば、殺人事件のニュースを我々が語る時でも、よく“今の子供たちは一体どうなっちゃったんだ”って言いますよね。子供が子供を殺したり、親を殺したり。“今の子供たちはおかしい”って言うんだけれど、そう言った時点で人ごとになっちゃうんですよね。
もしかしたらそれが快感だったんじゃないかとか、幸福だったんじゃないかとか。そういう可能性を考えるのはすごく恐ろしいことなんだけれども、そこに蓋をして、結局は人ごととしてやり過ごしている。
だからこの作品のように、“お前も客席にいるだけじゃすまない。こっち側のひとりになる可能性あるんだぞ”と。そういうメッセージを発している作品は必要だと思います。
高畑
だからと言って、この映画は難しいことを描いているわけではないんです。太田さんのような仕事の場合は基盤がどこにあるかといったら、普通の人の普通の暮らしでしょう。ここで脚本を書いたジャック・プレヴェールも、そういう普通の暮らしを大事にした詩人なんです。だからこそ、そういう生活を押しつぶす戦争や自由の抑圧には全力で反抗した。
雨が上がってパーッと晴れて今日は幸せとか、日々の生活や肉体も含めた男女の愛。そういう金持ちでも貧乏でも、どんな立場にいようが誰もが共有できるもので人間の生活は成り立っているんじゃないかと言っている人で、僕もそう思うんです。
でも、目標を達成するとか自己実現とか言われて、今みたいな生活をしていると、そういうものを忘れちゃうんですね。別にヨーロッパがすべていいわけじゃないけれども、日本に比べたら生活感が残っていると思うんです。
日本でも過去には虫の声に耳を傾けたり月を愛でたり、貴族から一般庶民までそういうことに幸せを感じていたんです。あるいはものの哀れを感じて心を動かされていた。日常を楽しむということに、かつての日本人は長けていたんです。でも今は、それが失われているような気がします。
太田
日本でそういう感覚が失われたのは、何か世界に肩を並べなきゃいけないとか。そういう強迫観念に囚われているからだと思うんです。戦争に負けて、今までの日本人の考え方はダメでしたとなった。そこから国を挙げて、先進国にならなきゃいけないという強迫観念に取り憑かれている。別に先進国になんかならなくていいのに。
司会
そういう経済至上主義が、普通の生活に基盤を置いた日本の文化を変貌させて、先ほど言われていた相手とコミュニケーションできない言葉の問題にも影響を与えたと?
太田
自分を出すことに対する恐怖心というのは、強くなっている気がしますね。例えばメールなんかでも、うちのカミさんから“あんた、バカね”とメールが来ると、立ち直れない(笑)。文字で見ると、すごく否定された気がするんです。でも実際に対面して“バカね”と言われると、表情や会話のつながりの空気とかで受け流すことが出来るんですよ。
そういうことに免疫のない子供なんかは、今のように文字の世界でのやり取りが多いとキツイでしょうね。誰かと会って話すということではなくて、相手に伝えるということをメールなどの文字で訓練することになる。そういう子供は自分を見せて相手に読まれるのが怖いから、文字による言葉の攻撃力を高めていっている気がするんです。
高畑
プレヴェールは仲間としゃべるのが大好きで、話し言葉でいろいろ表現する人だったんですね。それが一番大事。何かを理解するにしろ、自分が感じるにしろ、人間は言葉というものを武器にするしかないんです。その言葉を、どう使うかですよね。
太田
言葉というのは、本当にすごい力を持っている。こういう仕事をしていると、相方の田中との漫才のやり取りを作る過程で、僕は言葉の攻撃力をすごく強めていく作業をしているときがあると感じる時があるんです。
僕の発した言葉に反応して田中のことをお客が笑ったとする。すると僕が言った以上に、お客がその言葉で笑ったということが田中に返ってくるんです。つまり僕があいつを攻撃しているのではなく、お客が田中を笑うことで攻撃するように仕向けているわけです。相手が田中だと漫才だからいいんだけれど、僕が例えば村上ファンドのことを“あいつは、バカだ”と言ったとする。それでお客が笑ったら、今度は世間にそういう見方を呈示しちゃうことにもなるんです。
そういうことも含めて、自分がやっていることで人が傷つく可能性というのを考えざるを得ない。テクニックに長ければ言葉の攻撃力は強まっていくけれども、もうちょっとそれは緩めたほうがいいんじゃないか。そう思っている自分もいるんです。効果的ではないかもしれないけれども、そっちのほうが相手を守れるんじゃないかと。それをやっていくのは、すごく難しいと思いますけれど。
高畑
昔よりも、人は傷つきやすくなっている気がしますからね。自分も傷つきたくないけれども、他人を傷つけたらしっぺ返しが来る。だから出来るだけそっとしておきたいという時代ですから。そういうことでも太田さんのような仕事は、昔よりもやりにくい側面があるでしょうね。
司会
言葉をキーワードに日本の現状を語っていただいた感じですが、そういう社会や世界と照らし合わせてみても「王と鳥」は面白い映画だと思います。
司会・構成 金澤 誠
太田 光
おおた・ひかり1965年、埼玉県生まれ。お笑いタレント、漫才師。日本大学芸術学部中退後の1988年、田中裕二と「爆笑問題」結成し、同年「笑いの殿堂」でテレビデビュー。現在は妻・太田光代が手がける芸能プロダクション「タイタン」に所属し、テレビ番組、ラジオ番組のレギュラーを多数抱え、定期的にライブも行っている。2006年、芸術選奨文部科学大臣賞放送部門賞受賞。オムニバス映画『バカヤロー!4』(森田芳光プロデュース)のうち一本を監督。エッセイストとしての側面も持ち雑誌での連載のほか、『三三七拍子』『天下御免の向こう見ず』(以上、幻冬舎)、『カラス』(小学館)など著書も多数ある。
高畑 勲
たかはた・いさお1935年、三重県生まれ。アニメーション映画監督。1959年東京大学仏文科卒業後、東映動画へ入社。1968年の「太陽の王子ホルスの大冒険」が初監督作品。主な監督作品に「火垂るの墓」「おもひでぽろぽろ」「平成狸合戦ぽんぽこ」「ホーホケキョ となりの山田くん」など。2003年に公開された「キリクと魔女」(仏、ミッシェル・オスロ監督)の日本語版翻訳・演出を手がける。また、今年7月29日に公開の「王と鳥」(仏、ポール・グリモー監督)の日本語字幕翻訳を手がけた。
[ 公式サイト特別企画 ]
ポール・グリモーの言葉
高畑勲「王と鳥」を語る
宮崎駿「王と鳥」を語る
対談: 太田 光 × 高畑 勲 「王と鳥」と現代という時代
太田 光 「王と鳥」を観て
岩井 俊二 僕の「やぶにらみの暴君」
こうの 史代 気をつけたまえ、この映画は謎だらけだ
谷川 俊太郎 インタビュー
「王と鳥」とジャック・プレヴェールの詩的世界










