メニュー
ページ内容
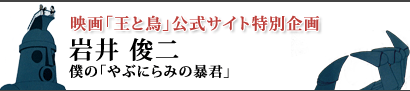
僕の映画「花とアリス」の中で、主人公の女の子とボーイフレンドがデートするシーンがあり、そのふたりが映画館で見ている映画が「太陽の王子ホルスの大冒険」でした。この映画を初めて知ったのは僕が幼稚園の頃でした。夏休み直前、肝油ドロップと一緒にこの映画の割引チケットが園児たちに配られたのを憶えています。見たくて見たくて親に泣きついたんですが結局連れて行ってもらえませんでした。ちょっと裕福な友達は映画を見れたばかりか紙芝居まで買ってもらい、僕はこの紙芝居をその友人にめくってもらって辛うじて見たつもりになったわけです。それから約十年後、高校二年の秋だったか、冬だったか。地元仙台で自主上映会があり、そこで生まれて初めてこの映画を見ました。その時はあまり大きなインパクトはなく、ああこういうお話だったのか、ぐらいでした。二度目に見たのはそれから二十年後、つまり今から五、六年ぐらい前でしょうか。ただなんとなく見たくなってTSUTAYAで借りて来て見たわけです。ファーストカットから度肝を抜かれました。唖然としながら一気に最後まで見てしまいました。その完成度の高さが理解できるのに二十年かかったわけです。
高校時代に僕を「ホルス」に誘ってくれた柴崎君は今で言うなら生粋のアニメオタクでした。当時はまだ「オタク」という言葉はなかったので彼のことをオタクと呼ぶ者はいませんでした。彼はオタクという言葉すら知らずに高校三年の夏にこの世を去りました。
彼によって僕は「ホルス」と再会し、「ルパン三世 カリオストロの城」を知り、そして「やぶにらみの暴君」を知りました。「カリオストロの城」はその後とある夏休みのアルバイトで映写技師の仕事をして何十回も見る羽目になり、しかしその経験は映画作りにおいて大いに勉強になったりしたわけですが、「やぶにらみの暴君」の方はついぞ見る機会がないまま現在に至る、というわけです。今回この「王と鳥」というアニメを見てこのコメントを書くという仕事を仰せつかり、 自宅でサンプルのVHSを一通り見てしまった後で、ネットでこのポール・グリモーという監督を調べてみたりしているうちにこの監督が「やぶにらみの暴君」の監督であることを知り愕然としました。しかもこの「王と鳥」が「やぶにらみの暴君」のディレクターズカット版であることを知り今度は呆然としました。ディレクターズカット版とオリジナル版の違いはともかく僕は亡き友柴崎の遺言のような「やぶにらみの暴君」をそれと知らずに見てしまったわけです。なんという運命の悪戯!
というわけで、やや動揺を隠しきれぬままこの原稿を書いているわけですが、柴崎が「カリオストロの城」と「やぶにらみの暴君」から僕に何を伝えたかったのかはもう火を見るよりも明らかです。前者が後者からあまりにも多くの影響を受けていることに議論の余地はないでしょう。ということはこの「やぶにらみの暴君」が日本アニメ界に与えた影響は計り知れないということになります。なにしろ「カリオストロの城」が日本アニメ界に与えた影響自体が計り知れないわけですから。
しかしそうは言いながらこのアニメはどう見ても日本のアニメとは違う。個人的には最近の日本のアニメの「動き」にどうも辟易していて、こういう海外の古いアニメの方が好きなんですが、その理由のひとつには、動きがリアルだから、というのがあります。いわゆるフルアニメとリミテッドアニメの違いというのはあるんでしょう。トレーシングという技法のせいもあるでしょう。しかしそれだけではなく、この時代のアニメには、こういう動きにはこのパターン、という「型」がまだ確立していない気がして、それが妙な生々しさを生んでいる気がするわけです。たとえば人間が歩く。どう歩くのか。人を歩かせてみる。それを描いてみる。こういうプロセスがいちいち存在し、しかもそれがまだ荒削りなので妙に生々しく見える。この生々しさがいまや逆に新鮮というか。
アニメ界では実写をなぞるなんていうのは邪道だという風潮があると誰かから聞いてがっかりしたことがあります。それは本末転倒だろうと思いました。アニメの原点とはなんなのか? それはそもそもモノがどういう風に動くのかなぞることじゃなかったのか? 進化しすぎたアニメ界はまるで現実から得るものはもはや何もないと思っているのか? まあそんなこともないんでしょうが、現在のアニメが大友克洋の絵と宮崎アニメの動きを手本に進化したのは否定できないことでしょう。それ以前のお手本は「鉄腕アトム」でしょうか。ミッキーマウスとかでしょうか。つまりマルに十字線をひいてから顔を描くやり方。これはアニメのみならずマンガにおいてもそうでしょう。この世界は一度マルに十字線に簡略化する技法の洗礼を受けている。そこから改めてリアリズムをルネッサンス的に復興しようとした。そこにやや無理がある。
そういえばミケランジェロのダビデ像はどこか不格好です。頭はデカいし手もデカい。わざとなんだろうか。後ろから見ると、なんか手抜きのようにのっぺりしてます。わざとだろうか。その真偽はわかりませんが、ルネッサンス期の絵画は結構苦労しています。なにしろその直前まで、リアリズムを完全に否定したマンガのような絵画が君臨していたわけで。いきなり手癖を直せと言われても難しかったんでしょう。
今のアニメ界もどこかそれに似たジレンマに陥ってる気がします。リアルを追求する反面、過去の表現方法の呪縛から逃れられない。僕らの子供時代のマンガの耳は、「6」でした。耳を描いて、その中に「6」という数字を描いていればよかった。でも今の写実的な劇画でそれをやったら違和感があるわけです。もう少しリアルに描かなければならない。ところがこれが案外いい加減。これは特にコミックに顕著な傾向です。描き手によって耳の種類は千差万別。「耳のカタチは人によって違う」なんて言う人もいるけど、100人の耳を並べたらほとんど識別できないくらいみんなおんなじカタチをしてるもんです。試しにその辺にいる人の耳をよく見て下さい。ひとたび簡略化されたものからリアルを復元するのはどうも予想以上に難しいみたいです。
「動き」に関してもなにか同じ問題を感じるわけです。今のアニメには確かに無駄がない。ソツがない。でもなにか胡散臭い。人がやった技だけが伝承され、なにか大事なものを見失ったかのような胡散臭さ。最近はCGやモーションキャプチャーも登場してまた見慣れない新鮮な動きが出て来たりもしてるけど、これはこれでどうも手間がかかってないように見えてつまらない。実写の世界もCGのせいで随分腰砕けな状況になってしまいました。「ポセイドンアドベンチャー」をCGを駆使してリメイクされても凄い気がしない。まあ難しい時代には違いないわけですが、この「王と鳥」を見てしまうと、なにかもう一度原点回帰できないものかと思ってしまうわけです。僕らの目の前に広がる世界を何らかのカタチで表現するのが芸術なら、この世界をどういう風に表現しようか、というあたりが原点であり、出発点な気がするわけです。鳥はどんな風に飛ぶんだろう、と考えたら、まずは鳥を観察するんでしょう。そしてなぞってみるんでしょう。いろんな試行錯誤があるんでしょう。そしてなにか面白い発見をしてゆくんでしょう。そこに作る感動があるんでしょう。僕はそういう痕跡が残っている作品がどうも好きみたいです。
「ホルス」を見て「カリオストロの城」を見て「やぶにらみの暴君」を見て熱狂していた我が友柴崎は「ナウシカ」を見ることなく「火垂るの墓」を見ることなくこの世を去りました。生きていたら今のアニメをどう思っただろう。まあ普通に生きていれば証券会社に就職でもしてハウルよりもナスダック平均株価が気になる平均的な中年になっているのかも知れないけど。でもきっと僕は奴に電話をして「やぶにらみの暴君」を見たことを報告するんでしょう。そして羊飼いの娘と煙突掃除の少年が絵の中から抜け出すシーンが如何に素敵だったかを熱っぽく語っていたんだろうと思います。
岩井 俊二
いわい・しゅんじ1963年、宮城県生まれ。横浜国立大学卒。1988年より音楽ビデオとCATVの仕事に携わる。1993年、テレビドラマ「ifもしも~打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?」で日本映画監督協会新人賞を受賞。1995年に「Love Letter」で長編映画を初監督。以降、「スワロウテイル」「四月物語」「リリイ・シュシュのすべて」「花とアリス」などを発表する。また、映画監督以外にも、庵野秀明監督の映画「式日」に俳優として出演、2002年ワールドカップの舞台裏を描いたドキュメンタリー「六月の勝利の歌を忘れない」の演出など、多彩な活動を続けている。
[ 公式サイト特別企画 ]
ポール・グリモーの言葉
高畑勲「王と鳥」を語る
宮崎駿「王と鳥」を語る
対談: 太田 光 × 高畑 勲 「王と鳥」と現代という時代
太田 光 「王と鳥」を観て
岩井 俊二 僕の「やぶにらみの暴君」
こうの 史代 気をつけたまえ、この映画は謎だらけだ
谷川 俊太郎 インタビュー
「王と鳥」とジャック・プレヴェールの詩的世界










