メニュー
ページ内容
2006年3月 8日谷川俊太郎インタビュー「王と鳥」とジャック・プレヴェールの詩的世界
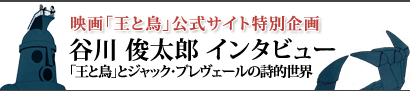
――
谷川さんは「王と鳥」のベースになった「やぶにらみの暴君」を一九五五年の日本上映当時ご覧になっているということですが、どういうきっかけでご覧になったんですか?
谷川
僕はアニメーションにはそんなに興味がなかったんだけれど、ジャック・プレヴェールっていうと当時は少なくとも僕の中ではもうヒーローだったからね。「天井桟敷の人々」なんかに感動してたから。ああいう社会性の高い大作映画の脚本も書けるし、短い幻想的な詩も書けるし、ドラマティックな歌詞も書ける。守備範囲がすごく広いんですよね。そのプレヴェールが脚本を書いたアニメーションだっていうので、みんな観に行ったっていう感じでしたね。ただ、題名とプレヴェールが脚本を書いたってことは記憶に残っているんだけれど、中味は憶えていないんですよ、全然(笑)。
――
今回「王と鳥」をご覧になって思いだされたことは?
谷川
なんとなくこの王様の顔に見覚えがあるなと(笑)。でも、筋立てなんて全然覚えていなかった。
――
では、逆にかなり新鮮?
谷川
すごく新鮮でしたよ。面白かったですね。ここのところ、彼の詩をあまり読み返していなかったし。やっぱり相当プレヴェール的な世界だから、久しぶりにそれを満喫したという感じでしたね。
――
プレヴェール的な世界というと?
谷川
すごくリアルな細部と、とんでもないファンタジーみたいなものが混ざりあっちゃっていて。この映画でも王宮の地下に下層都市っていうのがでてきますよね。プレヴェールっていう人は民衆の中から詩を書いていた人だから、ああいうものがでてくるんだろうなと思って。しかし同時にすごくSF的なところもあってね、巨大なロボットなんかはとても現代的で、それが最後にすべてを破壊しちゃいますよね。すべてを破壊するっていうのもすごくプレヴェール的だなと思うんです。あれって自由と反抗みたいなものですよね。
あと、やっぱり台詞。王様がエレベーターに乗っているとき、王宮のいろんな階にどんなものがあるかを説明するところがあるじゃないですか。あのいろんな部屋の名付け方なんてね、まさにプレヴェールじゃなきゃ、なかなかあんなことはできないんじゃないかなって感じがしますよね。
――
「夏監獄・秋監獄・冬監獄」とか「大人と子供用徒刑場」とか、かなりシニカルなすごい名前が並んでいましたね。
谷川
フランス語で聞く言葉の響きがきっと音的にも面白いんだと思うんですよ。それから、鳥の雄弁がまたすごいでしょ(笑)。ライオン達を説得するところのロジックの持っていき方なんて、すごく面白い。
――
羊飼いの娘はライオンのために羊を守っていた。王が娘をさらったので羊は逃げ狼に食べられたというところですね。
谷川
あのレトリックっていうのはやっぱり詩的だね。プレヴェールは、初期は散文詩の相当長いものを書いていたらしいから―僕はむしろ短い詩の方がぴんと来るんですけど、日本語訳で読むとね。たぶんああいう雄弁っていうのもプレヴェールの特徴なんじゃないかなと思いましたね。
――
アジテーションですよね。
谷川
そうそう。鳥っていうのは、本当はプレヴェールにとってはすごく大切な自由の象徴であって、それは人間よりももっと自由な存在だから、そんなに人間の言葉をしゃべらなくてもいいはずなんだけれど(笑)、その鳥があれだけしゃべるっていうことは、たぶんプレヴェールは、自由っていうものも言語によって獲得できるっていうふうに思っていたところがあると思うんです。詩をずっと書きつづけたのも、そういうことなんだろうと思うんだけれど。
言葉の力
――
谷川さんにとってのジャック・プレヴェールについて、もう少し教えてください。
谷川
僕は自分でも何度か書いているけれど、一時期プレヴェールに本当に惚れ込んでいましたからね。それでプレヴェール調の詩もいくつか書いているし。とくに小笠原豊樹さんがたしか60年代ごろに訳された『プレヴェール詩集』に本当に惹かれましたね。当時の日本の現代詩には全然見られないような詩で、フランス語で書かれた詩なのに日本語に訳されてもすごくピンとくる。小笠原さんの訳の素晴らしさのおかげなんですが、言語や文化の違いを超えた詩を感じましたね。
――
具体的には、どういう点にあったんでしょう。
谷川
詩を書く人って、多かれ少なかれ「詩的言語」みたいなものを信じているところがあって、普通の人がしゃべっている言葉でなかなか書けないんですよね。でも、プレヴェールの目は、普通の人が普通にしゃべっている言葉におりていて、本当にやさしい言葉で書いてあるんだけれど、発想や筋立ての中心にある彼の人生のとらえかたが、単純なのに胆が据わってるとでもいうのかな、とにかくアタマでっかちじゃなくて色っぽい。
簡単に言うと「世界は基本的に素晴らしくて美しい。だけれどそこに反抗しなければいけないものがいっぱいある」ってことだと思うのね。彼は反抗したいものは大いに反抗的に書くし、素晴らしい時には本当にあけっぴろげで素晴らしいって書くんですよね。それがやっぱり表現の仕方っていうのかな、レトリックっていえばいいか、彼の言葉の魔力で。プレヴェールが書いて小笠原さんが訳すと、彼の言葉の力は本当にすごいと思う。プレヴェールってそういう言葉の力があるから、凄く平凡なことを書いていても感動しちゃう。この映画の中でも、「世界が不思議」っていう小鳥たちが、歌う歌があるじゃない。あれなんかでも本当に単純なんだけれど、なんか説得されますよね。
――
「世界はひとつの不思議です。昼もあれば夜もあり 月もあれば太陽もあり 星もあれば果物もあり 風に回る風車も みんな世界にあるのです」と歌う歌ですね。あれは結局ロジックではなく、感情に訴えかける?
谷川
うん。基本的にはそうなんだけれど。感情に訴える訴え方の、デリカシーの工夫っていえばいいのか、面白さっていうのかな、思いがけない言い方をするのがね、すごく生きてますよね。僕はすごく惹かれました。こんな詩が書けるんだ、普通の言葉で、って。
プレヴェールは“世界”っていう言葉をよく使うんですよね。たぶんプレヴェールの影響を受けていると思うんだけれど、僕もわりと若い頃から“世界”っていう言い方をしていた。もっと若い頃は“コスモス”なんて言ってました。“宇宙”っていう意味だけれど。“世界”って普通あまり言いませんよね。日本では大体“世間”って言うんですよね(笑)。だから逆に言えば“世界”がちょっと新鮮だったんですね。世間じゃないんだ、世界だと。そうすると外国まで含んで宇宙までだって含めようと思えば含められるわけですよね。そういう世界っていう視点でこの世の中を見るっていうところが既に僕は詩的だっていう気がしますね。「世界は不思議」っていう歌なんか聞くと、まさにそういう世界を言ってるなっていう感じがします。
――
この映画の言葉に重きを置かれているように思うんですけど、言葉の力を谷川さんも信じていらっしゃるということですよね?
谷川
僕はあんまり信じていません。
――
そうなんですか!?
谷川
信じ方の中味ですね。信じているっていうふうには、もちろん言えるんですけど。
――
プレヴェールのようには信じていないということですか?
谷川
プレヴェールがどのように信じていたかなんて、僕にはわからないですよ。僕は詩を書きはじめたときから、言葉を使う“詩”っていうものに疑いがあった。「いったい詩で何ができるんだろう」と。それからもうちょっと広く詩を書きはじめてからも、言葉そのものにすごく疑問がありましたね。言葉って嘘もつけるし、大袈裟にも言えるし、ちっとも現実っていうものをきちんと捉えられないし、どんなに一生懸命言葉を使っても現実の三割も捉えられていないみたいなもどかしさをずっと感じていて、だから次々に自分の詩の形が変わっていったんだと思うんですよね。
――
今は?
谷川
今でも同じですよ。ただ以前よりも―つまりどこかの地点で言葉を信じないっていうのもけっきょく言葉で言うしかないわけだから―その一種の自己矛盾みたいなものを生きるしかないんだったら、言葉を信じないっていうことを前提にした上で信じるしかないって思うようになった。そこで少しはひっくり返りはしたんですけどね。だけど言葉っていうものを過大評価はしていません。
個人としての人間を見る視点
――
昨日、この「王と鳥」に関する対談を日本語字幕翻訳をした高畑勲監督と爆笑問題の太田光さんにして頂いて、高畑監督はこの映画の最後で塔が崩れるシーンを改めて見たときに9・11を思い出したと。太田さんは、そういうふうに考えるとこれはテロリスト側からの映画というふうにもいえるかもしれませんね、というようなことを話された。
谷川
そういう解釈もゆるすでしょうね。とにかく多義的な映画だから、いろんな解釈ができる。いろんなふうに見ることができるっていうのが、やっぱり良い作品の証拠だと思います。
――
その多義的な解釈の中で、谷川さんはどう?
谷川
この二人(プレヴェールとグリモー)は第一次大戦、第二次大戦を経験しているわけで、とくに第二次大戦はきっと大きな経験だったろうから、やはりヒトラー的な独裁者っていう含みで王様を書いていると思うんだけれども、その独裁者の肖像とかレリーフみたいなものが、映画の中で非常に機械的に大量生産されていますよね。ああいうのを見ていると、あれは確かにナチスのヒトラー的なマスの利用の仕方っていうものをある種象徴していると思うんだけれど、もっと深読みすると、独裁者=マスそのもの、画一化されたマス、つまり我々ね、大衆そのものっていうふうに見えるような気もしましたね。
――
王様はヒトラーだと見えましたけれど……。
谷川
一人の独裁者ではないみたいに見える。その独裁者を人間的な魅力をもって描いているのが、やっぱりすごく良いところなんですよね。もちろんチャップリンなんかもヒトラーを笑い飛ばしているわけだけれど、プレヴェールは笑い飛ばしているだけじゃなくてね、人間的な弱点みたいなものも描いている。とても孤独で、だから憎めない。一人きりの部屋で姿見を眺めて自分の容姿を気にしちゃったりして(笑)。
――
プレヴェールは王様も愛情を持った描き方をしてますね。
谷川
そうだと思いますね。体制とか組織っていうものがたぶん苦手な人だったから、人間を見るのにやっぱりひとり一人の個人を見るというのが彼の基本だと思うんですよね。だからこの物語全体もパターン的な対立に陥ってないというか。
――
絵から抜け出てきた王様の望みが羊飼いの女の子に愛されたいというのも、純粋で可愛いですよね。
谷川
だから王様の愛のほうがひたむきな感じがするよね。一見すると主役のような羊飼いの少女と煙突掃除の青年っていうのは、実は全然キャラクターがないのね。若い男女がただ愛し合ってますっていう決まり文句になってるだけで。煙突掃除人、どうしたんだよ? みたいな(笑)。
――
たしかに(笑)。多義性という点で、もう少し話していただけますか?
谷川
今の時代でも、地下の都市にいるような人達はたぶん世界中にいるだろうし、比喩的に言えばそういう人達と地上に暮らす人達との対立というのは、南北格差みたいな貧富の差という形でも、社会的弱者と強者という形でも、あるいは健康な人と不健康な人という形でも、いっぱいあると思うのね。しかも今の科学万能の機械文明みたいなものが、例えば原子爆弾をはじめとするような、暴力的な装置を発明しちゃっていますよね。それがやはりロボットに象徴されていてね、そういうものがもう善悪の区別なくとにかく破壊してしまうんだっていうふうな恐ろしさ。みんなもうメチャメチャに壊しちゃって、その廃墟の山でロボットが「考える人」になっちゃうのが、面白かったですね。
――
面白かったというと?
谷川
自分でもどうにも出来ないわけでしょう? 誰かにとにかく操られているわけでしょう? 後半は鳥がロボットを操っていましたよね。「お父さんは大丈夫なんだ」とか言って。鳥みたいに自由を象徴する、いってみれば良い方が操っているのに、とにかく差別なくメチャメチャにぶっ壊してしまったと。ロボットは自分には頭脳がないから、あそこで考えざるを得ない(笑)。だけど最後に鳥の檻をちょっと開けてあげて、その檻を踏み潰すことで、象徴的にある種の希望みたいなものを描いている。
――
いろいろ考えさせるラストですよね。
谷川
これは僕の解釈ですよ(笑)。ほんとは解釈なんかしたくないけど。
各場面が楽しくて、ほとんど本筋と関係がないような場面がすごく面白いじゃない。ライオンや虎がワルツを踊り出しちゃったり。盲目の黒眼鏡をかけた手回しオルガンを弾く男が、太陽まで鳥が飛んでったと、まるで見えるように言うわけでしょ。自分は見えないのに。あれだって目が実際見えていたって、見えないかもしれない、むしろ見えない人の方が想像力が豊かになっている時とかってあるよ、そういうものを理想化出来るんだみたいなメッセージもあの中に含まれているし。だからそういう意味で、僕はこの作品は、プレヴェールの詩みたいだって言ったんだけれど。プレヴェールの詩そのものがやっぱりそうなんですよね。すごく多義的なものが含まれていて。これはいい、これは悪いっていう割り切り方はほとんどないような気がするのね。
――
下層の人は南北もそうですけど、引きこもりみたいな…。
谷川
それもそうですよね。
――
どこかで、勝手にシャットアウトしちゃっている人達。
谷川
自分で自分をシャットアウトしちゃう人もいるし。
――
それと同じような感覚は谷川さんの中にもある?
谷川
あるからやっぱりそういうふうに思えるんだろうと思う。だからあの登場人物全部、なんか自分の分身みたいなふうにやっぱり見えちゃいますよね。王様的なものだって自分の中にあるだろうし、一種の権力欲とか支配欲みたいのもあるだろうし。
――
そう考えると、人を描いた作品?
谷川
そりゃそうですよね。しかも創り手自身が楽しんでね。
――
社会構造とか、反権力っていうよりは結局は人を描いたものという。
谷川
だからそれを性急に、例えば一時のマルクス、レーニン主義みたいなイデオロギーじゃなくて、古今東西歴史を通じてある人間の本質的なあり方みたいなものを描こうとしているっていうふうに思うんですよね。だからやっぱりこれ、相当昔の映画だけれど、今見ても新鮮に見えるっていう気がしますよね。高畑監督がおっしゃるように9・11を連想させるなんていうのはね、やっぱり変わらない人間の本性みたいなものを、プレヴェールっていう人は描いたわけだから。グリモーさんもそこのところをちゃんと押さえているんじゃないかな。変に割り切って見ちゃったらたぶんつまらないと思うんですよね。 (了)
谷川 俊太郎
たにがわ・しゅんたろう1931年、哲学者の谷川徹三を父に生まれる。詩人。都立豊多摩高等学校卒業。1952年、初めての詩集『二十億光年の孤独』(東京創元社)を刊行。以降『六十二のソネット』(東京創元社)『ことばあそびうた』(福音館書店)『みみをすます』(福音館書店)『はだか』(筑摩書房)『夜のミッキー・マウス』(新潮社)『シャガールと木の葉』(集英社)など、多くの詩集を刊行。一方、『マザー・グースのうた』(草思社)の翻訳で日本翻訳文化賞、作詞「月火水木金土日の歌」で、レコード大賞作詞賞など、絵本、作詞などの分野でも活動。「ハウルの動く城」の主題歌「世界の約束」の作詞者でもある。
[ 公式サイト特別企画 ]
ポール・グリモーの言葉
高畑勲「王と鳥」を語る
宮崎駿「王と鳥」を語る
対談: 太田 光 × 高畑 勲 「王と鳥」と現代という時代
太田 光 「王と鳥」を観て
岩井 俊二 僕の「やぶにらみの暴君」
こうの 史代 気をつけたまえ、この映画は謎だらけだ
谷川 俊太郎 インタビュー
「王と鳥」とジャック・プレヴェールの詩的世界










