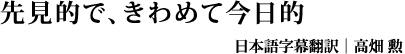メニュー
ページ内容
絵から人物が抜けだして現実を生きはじめる、面白い!学生時代、私はこの「王と鳥」の前身である「やぶにらみの暴君」という作品に夢中になった。もしこれを見なかったら、漫画映画の道に進むなどということは思いもしなかっただろう。
洗練された色彩と絶妙の遠近法、それが生み出す不思議な空間の魅力、奇想天外なアイディアの連鎖、人物の見事な性格描写、世界の強烈な垂直性、独特のユーモア。この映画は当時の既成観念をはるかに超えて、驚くべき斬新さでアニメーション映画の可能性を教えてくれた。
夢中になったのは、表現が素晴らしかったからだけではない。奇想天外なアイディアやイメージが、ただの奇想でもギャグでもなく、その裏に、現代史の重く冷厳な事実をひとつひとつ隠していることに気づいたからだ。
これは、単に独裁や抑圧からの解放をうたいあげるだけの古びた革命ファンタジーではない。一見矛盾や荒唐無稽に思える細部にこそ、じつは二十世紀が経験してきた「歴史」と「人間」の悲惨な真実が秘められている。そして作者は、次世代の私たちに、それをよくわきまえてこの世の「罠」に気をつけろ、と警告しているのだ。そうでなければ、どうして作者は第二次世界大戦直後に構想された「やぶにらみの暴君」を、わざわざ1970年代に「王と鳥」として蘇らせる必要があっただろう。
主人公のひとり、自由の象徴であるべき鳥でさえ、窮地に陥ればライオンたちを詭弁で扇動して立ち上がらせることも辞さない。そして蜂起したライオンたちが下層市街を通過すると、人々は「鳥たち万歳!」と歓呼する。勧善懲悪による素直な感動を期待しているヤワな私たちは冷水を浴びせかけられて、政治のリアルな冷厳さを思い起こさずにはいない。しかし同時に私たちは知らされる。窓からそれを見ていた老女が、首を振り振り「鳥ってものがこんなものだとは思ってもいなかったよ」とその現実を見抜いていることも。しかもこれらをすべて軽々とユーモラスに扱う。
強烈なメッセージを込めたラストシーンは別として、驚くべきは、三十年後の「王と鳥」でも基本的な思想に何一つ変更がないことだ。「やぶにらみの暴君」の優れたショットのほとんどが「王と鳥」にもそのまま残っている。1950年以前に発していた警告がいまなお通用するとは、なんと悲しいことだろう。
私は寄り目の王の中に、孤独で甘やかされた自己中心的な私たち現代人の似姿を見る。ロボットによって倒壊した高層都市の廃墟に、私自身逃げまどった空襲による一面の焼野原や、9.11の惨劇を重ね合わす。そしてその意味を問う。
作者の詩人的直感が喝破した「支配構造の垂直性」がますます強まっている現在、そのどこかに組み込まれている私たちがその現実に無自覚でいれば、暴走ロボットにいつ見舞われても不思議はないし、都市的なるものが崩壊したときその下敷きになるのは私たち自身だ。
少なくとも私にとって、「王と鳥」は、繰返し参照するに値する、先見的できわめて今日的な作品なのである。
1935年10月29日、三重県生まれ。59年に東京大学仏文科卒業後、東映動画へ入社。劇場用映画「太陽の王子ホルスの大冒険」(68)で初監督。主な作品は、「アルプスの少女ハイジ」(74)、「母をたずねて三千里」(76)、「赤毛のアン」(79)(以上、TV演出)、「パンダコパンダ」(72)「同、雨降りサーカスの巻」(73)、「じゃリン子チエ」(81)、「セロ弾きのゴーシュ」(82)、「火垂るの墓」(88)、「おもひでぽろぽろ」(91)、「平成狸合戦ぽんぽこ」(94)、「ホーホケキョとなりの山田くん」(99)。「風の谷のナウシカ」(84)、「天空の城ラピュタ」(86)のプロデューサー。著作には「『ホルス』の映像表現」、「話の話」、「木を植えた男を読む」、「映画を作りながら考えたこと」「十二世紀のアニメーション」(以上、徳間書店刊)。他に、プレヴェールの第一詩集「ことばたち」(ぴあ刊)の全訳、プレヴェールの詩によるシャンソン集CD「わたしはわたし このまんまなの」(ユニバーサルミュージック)の選曲・訳詞・解説も手がけている。