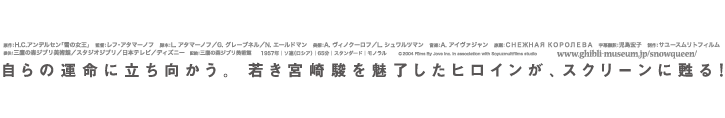Main Contents

「雪の女王」の中にあるロシア的なるもの
「雪の女王」新訳版字幕担当 児島宏子
“ライラック・ブリヴァール”に住むシュワルツマンさんご夫妻を10月初旬にお訪ねした。シュワルツマンさんは今年(2007年)87歳。「ミトン」や「チェブラーシカ」(両作品ともロマン・カチャーノフ監督)の美術監督、そして「雪の女王」(L・アタマーノフ監督)では亡きヴィノクーロフさんと一緒に美術監督を務めた方だ。お住まいは、モスクワの都心から少し離れた場所で、イズマイロヴァ公園の近くだ。
「ここはね、第二次大戦が終わって、少し落ち着いた頃に建てられた団地だ。皆で道を挟むブリヴァール(辻公園)にライラックを植えた。それが大きくなって、5~6月に花が咲く頃、素晴らしい香りが漂う……」
以前初めて訪ねたときにリョーリャ(シュワルツマンさんの愛称)が話してくれたことを思い出す。だから地名も“ライラック・ブリヴァール”となったのだ。とても古いような新しいような地名。
私の両親と同じような世代に属するリョーリャとターニャ(シュワルツマン夫人)。戦争が終わって、痛めつけられた国を、失うものは何もないという気持ちで再建に取り組んだ人々の中の若い世代。この人たちが、アニメーション「雪の女王」の制作にも携わったのだと気づき、私は、その人々の仕事からただ恩恵を受けてきた世代の一人なのだと、リョーリャの話に耳を傾けていた……。
1945年5月9日、ソ連(ロシア)は多大な犠牲(2千万人以上の戦死者)を払った結果、侵略国ナチ・ドイツに勝利した。この国を勝利に導いたスターリンは国民の大多数の敬愛を一身に受けた。だが彼は歴史の事実を改竄し1930年代に独裁体制を確立したことでも知られる。後にスターリン時代の様々な詳細を知らされた私たちは、一つの国がいかに矛盾に満ち複雑な様相を呈していたかと驚かされる。そのスターリンが孤独な死を遂げたのが1953年、翌年の晩秋に作家のエレンブルグは『雪どけ』と題する小説を書き、これは1955年春に発表される。スターリン時代に自己規制も含め、抑制され避けられてきた個人の感情表現を、エレンブルグはこの小説の登場人物たちに反映させ表現した。これは芸術の自由につながる重要な問題でもあった。小説のタイトル『雪どけ』は、ポストスターリンの時代状況を表す比喩として使われるようになった。そして1956年のソ連共産党の党内会議でフルシチョフがスターリン批判演説を行い、個人崇拝が否定される。翌1957年6月の中央委員会総会で今までのメンバーが入れ替わる。同年10月には世界初の人工衛星“スプートニク”が打ち上げられた。戦後の復興が目に見え、人々の気持ちが変化を喜び、わき立っていた1957年、「雪の女王」も登場したのだ。
「最も明るく喜びに満ちた時期だった」とシュワルツマンは回想する。
「1951年に私は国立モスクワ映画大学美術部を卒業したが、先生だったアタマーノフ(「雪の女王」監督)が学生の頃から目をかけてくれ仕事を手伝った……。彼はフョードル・ヒトルークの先生でもあった……」
こんな話を聞いているとめまいがしてくる。シュワルツマンもヒトルークも「話の話」や「霧の中のハリネズミ」の監督ノルシュテインの先生だ。ロシア・アニメーションという大河が目の前でうねって流れているような気がしてくる。
「雪の女王」でシュワルツマンはキャラクターを、少し年下のヴィノクーロフは風景を担当した。当時のソ連では国外に出るというのは全くの夢だった。まずソ連の通貨は多くの国で通用しなかった。“鉄のカーテン”という表現もあるが、いわゆるコメコン(経済相互援助会議)に参加している国以外からは排斥され、長い間、国交が回復されず平和条約も結ばれていなかった。この映画の原作はアンデルセンなので、アタマーノフ監督はデンマークを舞台にしたかったのだが、国交が回復していなかった。そこでアタマーノフ監督はカメラマンや美術監督二人を連れてバルト諸国へ出かけた。歴史上のいきさつもあり、これらの国々の街並みは最も北欧に似ている。ビリニュス(リトアニア)、リガ(ラトビア共和国)、ターリン(エストニア)などの諸都市で写真撮影やスケッチをした。1955年秋から1956年の初夏にかけてエスキースや絵コンテが準備された。そこから完成まで1年半かかったそうだ。
「この映画にかかわった誰もが善良だった。戦争や辛い生活をくぐって来ても、いや、そうだからこそ、ユーモアを忘れず、楽観して仕事に励んだよ。そうだ、未来があった。希望があった。世界がよりよくなる、そうできるという……」リョーリャの目のふちに、喜びと悲哀がにじみ仄かに赤くなった。
雪の女王のラスト、呪縛からカイを無事奪い返したゲルダ。二人はトナカイに乗って、春の息吹あふれる大気をつききる。お世話になった人々や動物たちへ感謝の言葉をかけながら。皆は微笑み慈しみの眼差しで二人を見送る。ゲルダとカイの喜びは私たちに清らかなカタルシスを投げかけ、私たちも思わず、一緒に「ありがとう」を唱和する─このエンディングは当時のソ連の人々が思い描いた、また私たちが心から引き継いでいきたくなる、また向かっていかなければならない未来を示しているのではないだろうか。
シュワルツマンは、クリスマスにモスクワで刊行されるという絵本『雪の女王』の挿絵原画50枚のほとんどを書斎に並べて見せてくれた。
その中に大きな鏡を数人の小悪魔たちが抱えて空に昇っていく絵があった。このシーンは映像ではとりあげられていないが、確かにアンデルセンの原作にはある。悪魔が何でもねじれて映る不思議な鏡を作った。悪魔はこの鏡を持って歩き、地上のあらゆるものを映してみる。それがすっかり種切れになると、鏡を持って天に登り、神様と天使たちをからかおうと画策する。しかし鏡は途中で落ちて粉々に割れる。その小さなカケラが人々の目や心にささり居座ると、人々はすべての物事を悪意を抱きつつ見るようになる。
アニメーションでは、そのような悪魔や彼の生徒である未来の小悪魔などは登場しない。
原作との違いということでいえば、原作ではゲルダが時おり古い賛美歌の一節を口ずさむ。その響きは、一つの節目を作り、読む側が思っていた以上の大きな役割を果たす。例えば、永久に凍ったようなカイの心を溶かすきっかけの一つにもなる。
だが映像ではこのような宗教性が全く表出されていない。歴史上の政治権力と宗教勢力の癒着という事実から生まれたマルクスの言葉《宗教はアヘンである》を、表面上受け入れる向きが世界中にあったし、今もある。そのせいだろうか? それともアンデルセンが生きた時代(1805~1875)と1950年代半ばという映画制作時との差異や、社会主義(実際にはソ連型社会主義)を建前にした国だからという理由によって、宗教性が排除されたのだろうか? そうかもしれない。だが、このアニメーションを何度も見て考えると、単純にそうだと言い切れない思いが迫ってくる。
映像の展開を見ていくとその奥深くに、私たちの目には見えにくいが、ロシア正教の心性が隠されているように思われてくるのだ。
同じキリスト教でも、カソリックには誇り高き精神が、ロシア正教には寛容の精神が見られる。
私が親しくしている信心深いロシア人のおばあさんは、性格の悪い(私たちに共通の)知人の女性のことに触れるとき、涙ぐみながら「かわいそうに」と言ったことがある。その女からひどい目にあっているのに! 私は吃驚して「なぜ、かわいそうなの!?」と叫びに近い声を出した。「そういう性格だから」と彼女は呟いた。「あの性格を直さない限り、幸せにはなれないから…。性格は簡単には変えられないから…。何と不幸な女だろう…」。彼女の言葉を聞き、その行為に接するうちに、私の人を見る目、人の受け入れ方が変わってきた。
私のことはともかくとして、今、「雪の女王」の中に私は、このおばあさんの面影、ロシア正教の寛容の精神を見出す。「ロシアの女こそ、心美人の典型だ」と微笑んだ音楽家がいたが、寛容の心をもつ心美人のひとりは「雪の女王」の中で「アイ、アイ…」とゲルダのために心痛めるフィンのおばあさんかもしれない。
雪の女王のまなざしにも“寛容”の光がよぎるのを目にしたと思うのは、私だけだろうか?
「雪の女王」で響くロシア語ほどうるわしいロシア語を聞いたことがないけれど、雪の女王の物言いも、震えてくるような美しさだ。声の主は、人民芸術家の称号や国家賞を授与されている女優マリーヤ・ババーノワ(1900~1983)。『森は生きている』(原題『12月』、この中の吹雪はまさに『雪の女王』を思わせた)初来日公演を成し遂げたコミサルジェーフスカヤ劇場付属の学校を出てから、メイエルホリド劇場、革命劇場(1957年よりマヤコフスキー劇場)などで大活躍した人だ。その彼女が巷で何よりも知られ、高く評価されているのが雪の女王の、声の役なのだ。
女王の声音には、春になれば姿を消す運命にあるひとの悲哀が込められていると感じる。春に象徴される“あたたかさ”に弱いひとが持つ、陰りのような響きがある。そしてまた、ゲルダのひたむきな愛情を前に、予想に反して、さりげなく引き下がる雪の女王のまなざしに光る“寛容”……。
ロシア的色彩が目につくのも、この作品ならではだ。
ゲルダのスカートの赤い色。冬が長く厳しいロシアでは誰もが、赤い色を生命力あふれる色と感じる。これは凍えている人々を温める炎の色。ロシアのフォークロアに登場する焚き火は、他者を思う愛情のシンボルでもある。凍えている人を招いて心身ともに温める友愛の象徴でもある。
それ故かロシア語で“赤い”は“美しい”と同意語である。首都モスクワの中心をなすものの一つ“赤の広場”は中世から、このように呼ばれている。中世になって、広場がより整備され美しくなったので、人々は赤の(美の)広場と言い習わすようになったのだ。
赤いスカートが、過酷な冬の嵐の中で火のようにゆらめく。それがゲルダのカイを思う熱い心と重なる。
いろいろな物思いに沈んでいると、ターニャ夫人が「新しいのを入れたわ。もう一杯、紅茶はいかが」とティーポットを持って来た。ふと見るとターニャ夫人は雪の女王を思わせる顔立ちをしている。美人で背が高くスマートな奥様と常々思っていたが。
そうだ、アタマーノフ監督はどんな人なのだろう?
「ハンサムで、身体も心も大きな人だったよ。機知に富み、とても愉快で、女にも男にも好かれた。大変知的で、それはすごい知識人だった……。何しろミハイル・ツェハノフスキー、ブルンベルグ姉妹、ムスチスラフ・パーシェンコの同時代人だからねえ……」
シュワルツマンさんの話はつきない。
彼が「雪の女王」のために手がけた多くのエスキースは、モスクワ映画博物館が所蔵し保管している。彼の展覧会が日本で実現する奇跡を祈りたい。
児島 宏子(こじま・ひろこ)
ロシアの芸術紹介にたずさわり、ロシア映画の日本語字幕を手がける。また、通訳としても日本とロシアの文化の橋渡し役を努める。訳書に『エイゼンシュテイン全集』共訳(エイゼンシュテイン キネマ旬報社)、『チェーホフが蘇える』(アレクサンドル・ソクーロフ 書肆山田)『すぐり』(アントン・P・チェーホフ 未知谷)『フラーニャと私』(ユーリー・ノルシュテイン 徳間書店)など多数。
第一回 鮮やかな記憶 ─ バレリーナ 草刈民代
第二回 洗練されたロシア版アンデルセン ─ 児童文学評論家 赤木かん子
第三回 「雪の女王」の中にあるロシア的なるもの ─ 児新訳版字幕担当 児島宏子
第四回 夢の力を持った作品 ─ シンガーソングライター 谷山浩子